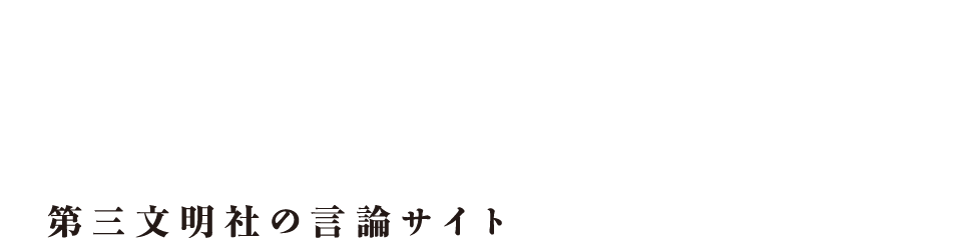「言葉への信頼」を腐らせているのは誰か
いささか刺激的な書名ではあるのだが、非常に丁寧に、そして誠実に作られた書物だというのが、読み終わっての率直な感想である。
ちなみにカバーの折り返しには、
これは勝ちたいリベラルのための真にラディカルな論争書だ。
ともある。
プロローグからエピローグまで、本書は一貫して問答形式で書かれている。
3・11以降、東京の高円寺や新宿で、やがて毎週金曜日の首相官邸前で、脱原発を訴えるデモが続いた。2015年夏には安保関連法案の可決反対を叫ぶ最大12万人ものデモが官邸を取り囲み、リベラルと呼ばれる知識人や文化人、メディアもこうした動きを支持し続けた。
まるで「アラブの春」が日本にも上陸したかのように巻き起こった「反戦・脱原発デモ」。かつてのように労組が動員しているわけでもなく、ヘルメットもゲバ棒もなく、SNSを使い、若者が前面に立ったオシャレな敷居の低さで人々を自発的に糾合したこれらの運動。
そこに集う人々自身が、これは〝戦前回帰を企図する危険な安倍政権〟と〝断固それを許さないリベラルな市民各層〟の戦いなのだと自負していただろう。
また、各社の世論調査でも5割を超す人々が原発再稼働と安保関連法案成立に「反対」と回答している。それなのになぜ、原発が再稼働され安保関連法案が成立したあとも安倍政権は依然として支持率を保ち、彼らリベラル勢力は安倍政権に勝てなかったのか。
本書で著者に問いを立てるのは、インタビュー記事でしばしば使われる「――」という表記のみで、特定の人物ではないのだが、徹底して著者の視点や論法には懐疑的で、手厳しく反論を試み続ける。あえてそうした緊張感を持った設定で議論を進め、著者は読者と共に検証と議論を深めようと努めている。
私は日本の知識人やメディアのなかでは、相当の勢力を保っているリベラル派が、「言葉への信頼」を腐らせている現状を指摘したいのです。(本書)
「リベラル」が勝てない3つの理由
著者は最初から最後まで、丸山眞男、柄谷行人、小熊英二、高橋源一郎、SEALDsら自身の公開された言説を丹念に拾い、検証する。そして、そこにこそリベラル勢力を劣化させている〝病巣〟が隠れていると指摘する。
著者の挙げる〝勝てない〟理由は大きく3点だ。
第1は、そもそも勝つ気があるのか、という疑問。権力を怯えさせるほどの実力を示せない運動には、権力を倒すことはできない。
第2は、行動の効果測定を避ける態度。目的と手段がいつの間にか転倒し、法案が成立しても敗北を認めて総括することなく、デモのある暮らしが理想であり、デモに集えたことが勝利だと讃え合ってしまう感覚だ。
第3は、大多数の生活者やビジネスマンの実感とかけ離れていることが理解できない認識。多くの国民は放射能や戦争を怖いとは思いながらも、それよりも景気や社会保障という目の前の現実を考えている。「あの戦争を繰り返すな」「戦争法案」というアピールは、叫んでいる人々の世界観を興奮させても、安倍政権をなんとなく支持する人々を振り向かせるものではなかった。それでもリベラルを自認する人々は、危機を訴える自分たちは目覚めていて、危機に目覚めない大衆は愚かな〝お花畑〟だと見ているのではないか。
本書のなかで、著者はキャラ作りをするかのように冷笑的に構えてみせたりもするが、終始そこには「権力」というものへの冷静でリアルな評価がある。
勝てばよいというものではない。すなわち、倒して済むものでもありませんよ。もちろん追従していればよいというわけでもない。権力はどうせならツールとして、世の幸せのために使いきるものでしょう。どうせなら、せいぜい酷使しなくちゃ。(本書)
今ある政権を倒したら、その倒した者が次の権力になるだけだ。世の中に〝善い権力〟と〝悪い権力〟があるわけではない。そもそも現代社会で権力とは与党や官僚機構の中だけにあるような単純なものではない。
権力とは、倒せと叫ぶのでも追従するのでもなく、むしろ世の幸せのために酷使するもの――。この著者の視点は、今の日本の政治を考えるうえで肝ではないのか。
ともあれ、保守であれリベラルであれ、反安倍であれ親安倍であれ、頭の体操をするつもりで一読を勧めたい本なのである。
価格 //発刊
→Amazonで購入