第112回 正修止観章 72
[3]「2. 広く解す」70
(11)病患境④
(2)別釈③
「病患境」は総釈と別釈の二段に分かれている。その別釈は、「病を観ずるに五と為す。一に病の相を明かし、二に病の起こる因縁、三に治法を明かし、四に損益(そんやく)、五に止観を明かす」(第三文明選書『摩訶止観』(Ⅲ)、近刊、頁未定、大正46、106b13~14)とあるように五段に分かれているが、今回は、第五段の「止観を明かす」について紹介する。 続きを読む

(2)別釈③
「病患境」は総釈と別釈の二段に分かれている。その別釈は、「病を観ずるに五と為す。一に病の相を明かし、二に病の起こる因縁、三に治法を明かし、四に損益(そんやく)、五に止観を明かす」(第三文明選書『摩訶止観』(Ⅲ)、近刊、頁未定、大正46、106b13~14)とあるように五段に分かれているが、今回は、第五段の「止観を明かす」について紹介する。 続きを読む
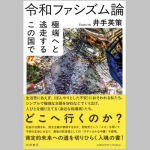
著者の井手英策氏は、弱者を生み出さない社会政策「ベーシックサービス」の提唱者として知られている。本書は、戦前の日本とドイツの財政史をたどりながら、現在の日本社会が陥っている危機の本質を探り当て、その克服の方途を探ったものである。
よくおぼえておいてほしい。
財政とは社会をうつしだす鏡である 。この本は、経済史でも、政治史でも、社会史でもなく、財政史という一風かわった、そして多くの研究者が使いこなせなかったメスをもちいて、日本社会の病根をえぐりだしていく。(本書13ページ)
著者はなぜ、ふだんあまり耳にすることの財政史という視点にあえてこだわるのだろうか。そもそも財政という用語はなにを意味するのか。
現在、世界の多くの国々は民主主義といわれる社会体制のなかで暮らしている。労働の対価として収入を得て、市場からモノやサービスを購入することによって生活を営んでいる。だが得られる収入には格差があり、また病気やケガなどの理由で働くことのできない人も存在する。こうした状況を放っておけば、弱肉強食の世の中になり、共同体は分断され、社会的秩序は崩壊してしまう。 続きを読む
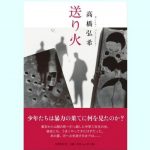
高橋弘希(たかはし・ひろき)著/第159回芥川賞受賞作(2018年上半期)
選考委員の小川洋子が「他の候補作を圧倒する存在感を放っていた」と述べた高橋弘希の「送り火」。
津軽地方の山間部にある、時代から取り残されたような過疎地域。生徒数の減少で廃校となる予定の中学校に、東京から越してきた主人公の歩。父親の仕事の影響で転校には慣れている彼は、新しい中学校でも要領よく同級生と馴染んだかのように見えたのだが、そこには歩がこれまで見聞きしたこともない、おぞましいほどの暴力の連鎖が隠されていた。
選考にあたっては意見が二分していたようだが、その焦点となったのはまさにその暴力。否定的な意見で多かったのは、作者がその暴力を通して何を描こうとしているのかが分からないという意見である。 続きを読む

(2)別釈③
③「治病の方法を明かす」
この段は、「治法の宜対不同を明かす」と「正しく治を用うるの不同を明かす」の二段に分かれている。 続きを読む

大垣書店の京都市内各店舗で、2月28日(土)まで大垣書店フェア『心の深奥へ、思考の旅へ。一冬の終わりに「私」を聴く読書』を開催しています。
大垣書店は、全国にグループ50店舗以上を展開する創業昭和17年京都発の地域密着型書店で、学術書や人文書をはじめ、一般書、文庫、新書まで幅広いジャンルの本を取り揃えています。
この2月のフェアでは、京都市営地下鉄烏丸線沿いの店舗である、イオンモールKYOTO店、烏丸三条店、京都本店、イオンモール北大路店、佛教大学店、高野店など6店舗でフェア展開しています。
興味のある方は、ぜひお近くの大垣書店にお立ち寄りください。 続きを読む