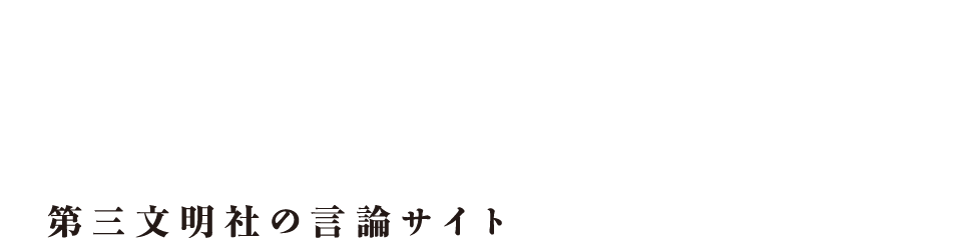人間が人工知能を生み出そうとする根底には、自分の似姿を作ろうとする本能があるのではないか。著者はそう述べる。確かに将棋で話題になったように、人工知能はある側面では人間をすでに凌駕している。それでも人工知能は、人間には容易にできる多くのことがいまだできない。人工知能は、人間とどのように異なっており、何ができて何ができないのか。それを解くためには、人工意識とクオリアをめぐる問いを掘り下げる必要がある。本書は、このような問題意識を機軸に人工知能の未来を考えていくうえで、重要な論点を浮き彫りにしようとしたものである。
ビッグデータに基づく統計的な学習で知性を高めていこうとする人工知能研究では、人間の知性の本質を捉えることはできないと著者は主張する。たとえば、「赤」の「赤らしさ」や「水」の「冷たさ」といったクオリアを生み出すもの、目の前で見ている薔薇を美しいとか禍々しいと感じる意識を生み出すものは、「今、ここ」で起こっている神経活動、その相互関係であり、それを一体として支えている身体性である。私たちが主観的に体験する世界は、個別性を中心に回っている。私という固有の存在、私が死ねば二度と戻らないという自己意識に関する「セントラルドグマ」。この薔薇があのときの薔薇と違うという記憶。それらは、固有の時間性・空間性・身体性を基盤としている。人工知能は、それらの個別性をデジタルデータとして統計的に解析し、世界をフラットに捉える運動と共にある。だがそのような人間の個別性から遊離した方法では、人工知能の先に「人工意識」は拓けないと著者は結論づける。
本書は、著者が十六年を費やした労作である。人工知能や人工意識に関するこれまでの研究動向や到達点を整理し、その限界を指摘した本書は、シンギュラリティーによる社会の変容を議論する手前で、私たちはまず人類そのものの研究を見つめなおす必要があることを気づかせてくれる。