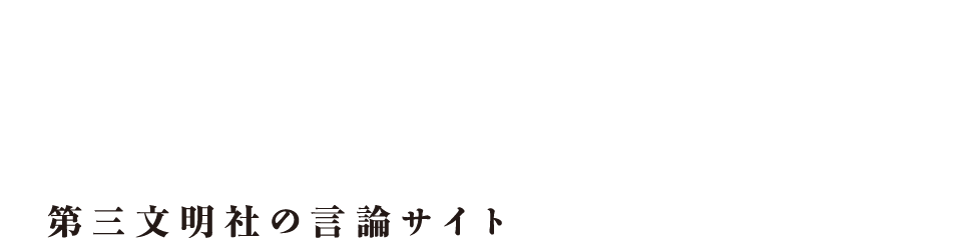被爆体験を継承するための重要な一書
2015年に新たに上梓された『語りつぐナガサキ――原爆投下から70年の夏』は、前年に出版された『男たちのヒロシマ――ついに沈黙は破られた』につづく長崎編と呼べるものだ。
『ヒロシマ』は表題のとおり、男性のみによる証言集だったのに対し、長崎編には男性・女性の体験から成っている。
本書では巻末に、被爆医療専門家2人の感想が「被爆証言を読んで」とのタイトルで付されている。そのうちの一人、長崎原爆病院の朝長万左男(ともなが・まさお)名誉院長が、「家族を亡くし、自らの健康を損ない、財産を失い、経済的にも恵まれなかった70年の人生は、14人の方々それぞれに多様ですが、原爆によって狂わされたという一点だけは共通」と述べていることに象徴されるように、1945年8月9日午前11時2分の出来事によって、人生を変えられたことが証言者たちに共通する前提となっている。
その上で本書では、多くの証言者がいつ原爆の後遺症が出るのかという不安におののきながら戦後70年間をすごしてきた事実や、特に子どもの出産の際、母親であれ父親であれ、奇形児が生まれるのではないかとの強い葛藤に悩まされてきた事実などが浮かび上がる。
夫から「被爆者には黒い赤ちゃんが生まれるという話だ」と告げられた妻が、夫に被爆体験を告白することもできないまま、健康な子どもが生まれることを必死に願い、もしも黒い赤ちゃんが生まれたらその子と一緒に死のうとまで思いつめて出産に臨んだ話。そうして生まれてきた赤ちゃんは、色白で、太った元気な女の子だったことがわかり、「嬉しくて、嬉しくて、声を上げて泣いた」と体験者は綴っている。この種の話は、本書で何度も登場する。
放射線による健康障害は自身の肉体を蝕んだだけでなく、子や孫たちへの影響までも思い悩むしかなかった被爆者たちの実態は、放射能汚染にまつわる特有の問題だ。
そうした体験は、家族だからこそ逆に、語れなかったという告白としても紹介されている。
反面、本書では「初めて被爆体験を語った」という証言者も複数登場する。そのうちの一人は、「本当は、いまでもできることなら思い出したくはないのです」と、その複雑な心情を素直に語っている。
核兵器の本質
長崎編の本書では、爆心地にもっとも近い国民学校として知られる城山国民学校(現在の長崎市立城山小学校)に在籍していた男性の証言も寄せられている。1500人近くいた同校の児童は、被爆後、100人足らずしか生き残っておらず、在校生の93%が亡くなったという冷徹な事実が紹介される。
また直接被爆していないにもかかわらず、片付けなどのために爆心地に入った人たちが原因不明の病気で入院したり亡くなったりする「入市被爆」の知識を持たないまま、被爆直後に爆心地に入ってしまった女性の体験のほか、母親のお腹の中にいて被爆した「胎内被爆児」の体験も胸に迫る。
結核療養所に入院していた母親に月に1回、祖父に連れられて会いに行く少女。実は両親が離婚した理由が、母親自身の原爆後遺症によって父親の一生を狂わせたくないという母親の善意の気持ちからであったことを、後になって初めて知ったときの娘の気持ちなど。
さらに本書でも、在日韓国人として被爆した女性の体験が収録されている。長崎では当時7万人いたとされる朝鮮人のうち、2万人が被爆、1万人が死亡したといわれると記されている。その数の多さにびっくりさせられる。
なお本書においても、日本語だけでなく、巻末には英語訳が全文掲載されており、世界の読者に届けることが可能な構成となっている。
冒頭で紹介した朝長名誉院長は、「1945年8月に瞬間的に被爆したことで、70年の生涯にわたって持続するこの諸々の影響を免れ得ないことが、まさに核兵器の本質」とも指摘しているが、こうした兵器がいまも世界中に無数に存在している現状をふり返るとき、被爆体験を持つ日本人に託された使命を、読者は感じとらずにはいられないはずだ。
戦後生まれが国民の8割に達したという現在、本書は被爆体験を継承するための、一つの重要なツールとなるだろう。
「反戦出版」書評シリーズ:
シリーズ① 『男たちのヒロシマ――ついに沈黙は破られた』
シリーズ② 『語りつぐナガサキ――原爆投下から70年の夏』