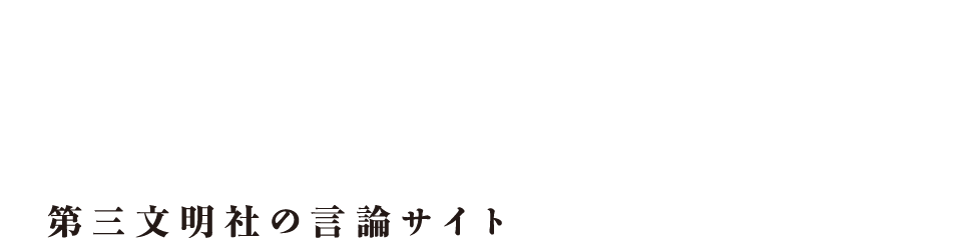36歳のデビュー作
ウォルト・ホイットマンは、およそ200年前の1819年、農夫ウォルター・ホイットマンの次男として、ニューヨーク州ロングアイランドに生まれた。
じつは父親が自分と同じ名前を彼につけたので、正しくはウォルター・ホイットマン・ジュニアということになる。
父親はまもなく大工に転身したものの一家の生活は苦しく、ウォルトも11歳から弁護士事務所の雑用係として働きはじめる。その後、見習いを経てニューヨークで植字工となるが、大火で職場の印刷所を失う。故郷に戻って小学校の教師をし、再びニューヨークに戻るとジャーナリストや印刷業などで身を立てていた。
こんにち私たちが知る〝詩人〟ウォルト・ホイットマンが世に出るのは、彼が36歳なった1855年のこと。そのデビュー作が詩集『草の葉』である。
わたしはわたし自身を称揚し、またわたし自身をうたう、(富田砕花・訳)
この書き出しではじまる「わたし自身の歌」は、ホイットマンが1855年の初版本の巻頭に掲げた長編詩だ。富田砕花訳の本書には、その完訳が収められている。
アメリカの精神革命
詩集『草の葉』が登場した19世紀半ばは、アメリカ文学の大きな転換期だった。批評家マシーセンはこの時期を〝アメリカ・ルネサンス〟と位置づけている。
すなわちこの時期、エマソンの『代表的人間像』(1850年)、ホーソーンの『緋文字』(1850年)、メルヴィルの『白鯨』(1851年)、ソローの『ウォールデン』(1854年)、そしてホイットマンの『草の葉』(1855年)など、のちの世界的文学となる作品が続々と誕生したのである。
ちなみに日本にペリーが黒船を率いて最初に来航し、開国を求めたのが1853年だ。
ソロー協会の会長を務めた碩学ロナルド・ボスコは、池田大作SGI(創価学会インタナショナル)会長との鼎談集『美しき生命 地球と生きる』(毎日新聞社)のなかで、
私は、アメリカ・ルネサンスを、アメリカにおける知性と想像力の、過去からの独立戦争と解釈しています。
と述べている。
18世紀末のイギリスからの独立戦争に勝った新大陸の人々は、この19世紀半ばの精神革命というべき文芸の勃興によって、真の意味で古い旧大陸の思考から独立し、〝新しいアメリカ人〟としての精神を獲得する。
その精神革命としてのアメリカ・ルネサンスが、奴隷制の廃止をめぐる南北戦争(1861年~65年)へと時代を押し上げたのは、必然の帰結だったといえるだろう。
無名のジャーナリストであったホイットマンは『草の葉』初版を出すにあたり、アメリカ・ルネサンスの中軸にいたエマソンに草稿を送っている。エマソンはただちにこれを絶賛する手紙を届けた。
全一なるものへの志向
ホイットマンの詩は伝統的な形式にはまらない自由詩だった。大統領から兵士、奴隷や娼婦まで謳いあげ、生と死を、労働を、政治を、男を、女を、自国を、まだ見ぬ異国を、大地と太陽を、すべての存在をあるがままに慈しんだ。
世界の個別に分け隔てなく目を配りながら、そこに何か差異を超えた大きな全一なるものを見ようとするかのようだった。
彼自身の家はキリスト教クエーカー派ではあったが、その目に映る生命観と世界観は、むしろ東洋的なものにこそはるかに響き合うように思われる。
1869年にスエズ運河が開通し、アフリカ南端を回らずに地中海からインド洋に直結する航路ができると、詩人は長編詩「インドへの航旅」を綴り、1876年刊の『草の葉』第6刷に加えている。本書の最後に置かれたのも、この「インドへの航旅」である。
おおらかに生命の多面性と多様性を讃えた『草の葉』は、当時としては斬新であると同時に十分に異端であった。ジェンダーにとらわれないかのような率直な人間愛を綴ったことで、反道徳的だとして常に批判にもさらされ続けた。
全米で同性婚が合法化され、一方で分断に揺れる今のアメリカを、ホイットマンの魂はどんな思いで見つめているだろう。
彼の生涯にとって、この詩集は特別なものだった。雑音に屈せず、晩年まで繰り返し改稿し、新たな詩を加えては版を重ねて刊行し続け、1892年の逝去の直前に「臨終版」となる第9版を出している。
今般、第三文明社から刊行されたこの『詩集 草の葉』は、詩人・富田砕花(1890年~1984年)の訳によるもの。
富田が最初に『草の葉』を訳したのは1920年頃で、青年時代より富田訳の『草の葉』を愛読してきた池田SGI会長の提案を受け、1971年にグラフ社から『詩集 草の葉』として再刊している。
このたびの第三文明選書12としての再刊は、そのグラフ社刊版を引き継いだレグルス文庫『詩集 草の葉』の初版第7刷(2000年)を底本としたものである。
巻頭には、1971年のグラフ社刊版に池田会長が寄稿した一文「『草の葉』に寄せる」が、また巻末には同書に富田が会長への感謝などを綴った「後記」が、それぞれ再録されている。
おお、わたしの勇敢な霊魂よ!
おお、さらに遠く、さらに遠くへの帆走!
おお、大胆な歓喜、だが、安全な! それらはすべて〝神〟の海洋ではないか?
おお、さらに遠く、さらに遠くへの帆走!
(「インドへの航旅」)