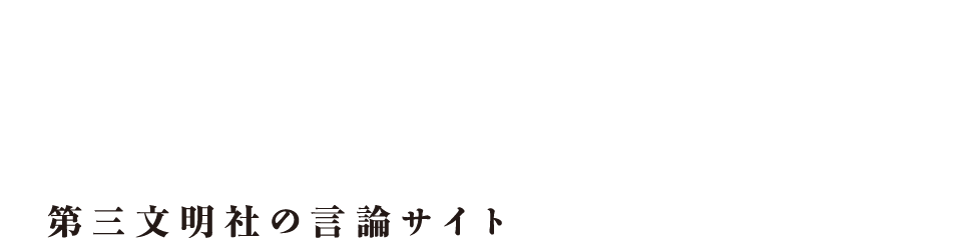「幸福書店」の閉店
この2月、〝本〟にまつわるニュースがいくつか駆けめぐった。
東京・代々木上原駅前の書店「幸福書房」が、2月20日に閉店した。1977年に創業し、80年から同地に移転。近隣に住む作家の林真理子氏は、駅前にこの本屋があるのを見たことが、ここに転居を決めた理由の一つだったと述べている。
林氏のブログなどにたびたび登場するほか、ここで林氏の本を買うと書店が預かって林氏のサインをもらっておいてくれることもあり、真理子ファンの〝聖地〟でもあった。
家内経営していくには経営者が高齢になったことや、テナントとの契約が切れたことなどが閉店の主な理由には挙げられているが、やはりなんといっても書店の経営そのものが厳しい時代に入っているのだ。
2月26日に全国大学生協連合会が発表した2017年の「学生生活実態調査」は、1日の読書時間がゼロという大学生が53.1%と、ついに過半数になったことを発表した。
同じ日、出版科学研究所は2017年のマンガ市場規模について、単行本の電子書籍版の売り上げが、ついに紙を上回ったことを発表した。単行本と雑誌を合わせた「紙」は前年比で12.8%という落ち込み方で、16年連続の減少となった。
書店減少の最大の要因とは
本書のプロローグにも、書店業界の深刻な状況が綴られている。
1999年に22296店あった日本の書店は、2017年5月現在12526店になった。17年間で43%以上もの減少である。
単純計算で毎年500~600店ずつ書店がなくなっていたことになる。(本書)
もちろん町から書店が消えゆく背景には、2000年にアマゾンという巨人が日本に上陸し、今や紀伊國屋書店などを抜き去って〝売上高日本一の書店〟になっていることなど、ネット書店の登場やコンビニでの雑誌販売の影響も大きい。
だが本質的な最大の原因は、やはり出版市場全体の急激な縮小なのだ。
過去のピークだった1996年の2兆6564億円と比べると、2016年には1兆4709億円と、5割近く減少した。
とくに大きいのが雑誌の売り上げ減で、主に雑誌の売り上げによって経営が支えられてきた町の書店にとって、これは致命的な打撃となった。
業界の構造的な問題
こうした逆境にある書店を何とか応援できないかという思いで、著者は2年をかけて全国およそ100の書店を歩いた。
著者は出版流通専門誌の記者を経てフリーランスになった人で、いわば本と書店に関する目利きの玄人である。
著者の前に現れる、苦戦するなかでも工夫を凝らして健闘していたいくつかの書店が、それでもやはり経営が困難になっていく現実。しかも、従業員の再就職や取引先との関係などで、経営難に陥ってもなお、すぐに廃業することさえ難しい現実。
町の書店の経営をこれほど不安定にしているのは、前述したように高度成長期に確立された旧来の経営モデルが雑誌の売り上げに大きく依存していたこと。一方で再販制度によって本は定価を値引くことができず、おまけに小売業界としては粗利率が異常に低いことだ。これでは賑わっているように見える本屋でさえ、家賃と人件費の捻出で息が切れる。
小売業では、販売価格から仕入れ原価を引いた粗利益率は40パーセント前後というのが一般的だ。パンや菓子の製造小売りなら60パーセント以上、技術を売る眼鏡店なら70パーセント近くになる。ところが、書店の平均的な粗利率は22パーセント前後に過ぎない。(同)
こうした業界の構造そのものを変えないかぎり、書店の衰退は続くだろう。地域に書店が1軒もない無書店自治体も増え続けている。
〝生き残る本屋〟の共通点
とはいえ、著者は悲観的な思いでこの本を綴ったのではない。むしろ現状を伝えることで、書店の存在があらためて注目され、書店を作りたいという人を増やしたいという思いを乗せて綴った。
町の書店が置かれた想像以上の厳しい現実が見えてくる一方で、地域住民とのコミュニケーションのなか、よろず屋的な役割を担うようになった書店なども登場する。
また東日本大震災で被災した書店の〝その後〟についても、著者は丹念に足を運ぶ。そこで見えてくるのは、街の復興あるいはゼロからの街づくりにおいて、書店こそがコミュニティの中核になるという事実だ。被災地で自ら書店を立ち上げようとする1人には、作家の柳美里さんもいる。じつは著者自身の故郷・福島県の小高町(現在の南相馬市)も、原発事故で避難区域に指定されている。
独自の選書眼で大型店に対抗しようとする書店主。空き家再生プロジェクトとコラボする書店主。読み聞かせの場として地域の活字文化そのものを育てようとする書店主。本書にはさまざまな事例と悪戦苦闘も紹介される。
エピローグには、山陰で始まっている「本の学校」が登場する。ドイツのシステムを参考に、本物の出版人を育てようとする取り組みは興味深い。
これまで著者が書店主や書店員からしばしば聞かされてきたのは「棚で会話する」ということだった。
客と直接言葉を交わすのではなく、棚を通して客を惹きつけ、驚かせ、唸らせ、満足させるのが理想の書店というわけだ。
だが全国の書店を歩くなか、著者はあることに気づく。この過酷な状況下で生き残っている書店の共通点である。
むしろ積極的にお客と会話する書店こそが生き残っているかのようだ。(同)
これからの本屋がどのような形になっていくのか、なるべきなのか。読む人それぞれにヒントが見えてくる一冊だ。