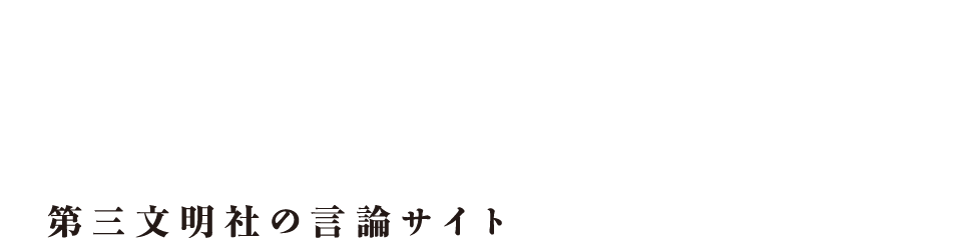著者は、ゆとり教育を推し進め、日本の子どもたちの学力低下をもたらした元凶として、批判されることのほうが多い。
しかし、それは世の中がまだ著者の理念に追いついていないからだと私は考えている。
このたび、古巣である文部科学省の歴史と現状を分析する本を出して、教育政策について落ち着いた議論をするよう訴えた。
追いつき型近代化の達成を受けて1980年代から、自明の国家目標を追求するのではなく、1人1人の人間が、問題自体を立て、正解のない問いを考え続ける営みとして、教育を捉え直す動きが始まった。
著者によれば、いわゆるゆとり教育はそうした積み重ねの上に打ち出された新機軸であった。
政治学者である私にとっては、文科官僚と政治の関係、キャリアとノンキャリアの関係に関する記述が極めて興味深かった。
政治家の方向付けの中でアイディアを凝らして政策を作るという本来の官僚が文科省にずっと存在したという著者の指摘は、私の偏見を取り去った。
著者にとっての最大の不幸は、ゆとり教育という言葉が日本の若者の学力低下という現象と結合されている点にある。
たとえば、芳沢光雄氏の『論理的に考え、書く力』(光文社新書)を読むと、最近の数学教育では、比の概念を教えない、幾何の証明問題の訓練をしないなどの理由で、若年層において論理的にものを考える能力が著しく低下していることが実証されている。
しかし、それはゆとり教育の問題というより、大学入試の在り方、あるいは入試を事実上放棄して大学が学生を囲い込むようになったことなどが主たる原因であろう。
著者にすれば、そうした論理的思考能力を育むためにこそゆとり教育を進めたと言いたいはずである。
著者が言うように、教育改革に拙速は禁物である。
グローバル人材などという意味不明の流行語に踊らされては、日本の教育の未来はない。
国民の論理的思考力を高めるためにどのような教育が必要か、具体的事実に即して議論することが緊要の課題である。