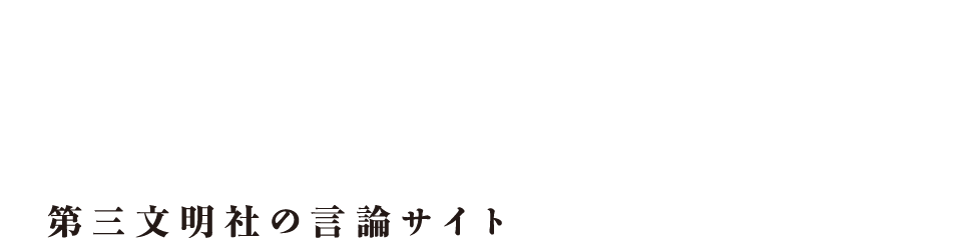優れた作家の文章は、常にやさしい。自分を見てくれて、わかってくれて、言葉をかけてくれる。だから、読者にとって作家は、最大の理解者になりえるのだ。
現代における雨宮処凛という作家は、きっとそんな存在なんだと思う。
日本の社会は、人が生きるのにあまりにも窮屈で息苦しい。低賃金で働かされる労働者は声を発することさえ許されず、地方のお年寄りは原発事故や災害によって見捨てられたように簡単に土地を追われる。若者たちは恋愛ですら、婚活というデータに管理されてしまっている。
若かった頃の雨宮処凛も、そんな社会の底辺でもがき苦しみながら生きてきた女性だった。いじめられ、家出をし、自殺を試み、水商売や右翼団体に身を投じてなんとか自己を保ってきた。だからこそ、社会の暗闇の中で嗚咽して身を震わせている人々の胸の内をわかっている。
本書の一文である。
奪われた当事者性を取り戻すにはどうすればいいか。簡単だ。怒ればいいのだ。
沈黙していれば社会の圧力に押しつぶされるだけ。抜け出すには、怒りが必要だ。
でも、雨宮処凛は誰よりも知っている。多くの人々が、それをするだけの勇気も力も仲間も持ち合わせていないことを。だからこそ、彼女はそういう人の傍らに立ち、励まし、代わりに怒ってくれる。
その半面、彼女は弱っている人々にはやさしい。飼い猫の生活を例に、こう語る。
猫は他の猫と自分を比べて幸せだと思ったり不幸だと思ったり、そんなことはしない。だからいつも自信たっぷりで堂々としている。(中略)そして気づくのだ。自分自身も子供の頃はそうだったのだと。
君だって日だまりで眠る猫のように楽に生きていいんだ。それがこの日本で生き延びていく方法なんだ。雨宮処凛はそう語りかけてくれるのだ。
九十八篇のエッセイの一つひとつは、冷徹な社会で凍える人々にとって、お母さんがつくってくれた温かなスープのように染み込み、心を火照らせてくれるはずだ。