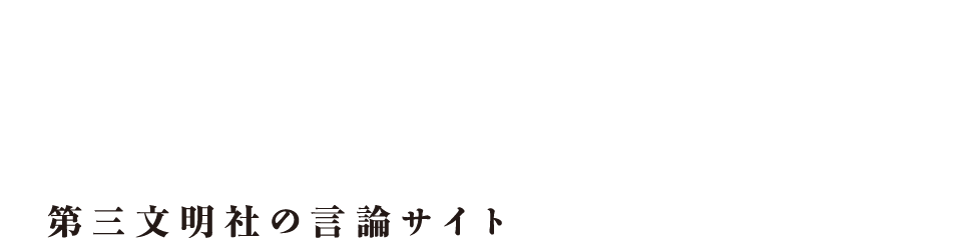日本橋・人形町で暮らしていた5年前、築30年ほどのワンルームマンションに住んでいました。そのマンションの入居者の大半はビジネスパーソンでしたが、何名か、一人暮らしの老人が住まわれているようでした。何度かゴミ捨て場ですれ違っただけで、結局、彼らの名前を知ることはありませんでしたが……。
――彼らは今どうしているのだろうか。倒れたとき、助けてくれる人はいるのだろうか。
あの老人たちが孤独死したとき、隣人はどう感じ、どう行動するのだろうか。見ず知らずの老人の死によって、日常は寸断され、戸惑うのだろうか。それすらも無関心でいられるのだろうか。
いや、何も死にゆくのは老人たちだけではない。幼い頃に、ぼくは心臓の病を患っていた。最悪、ワンルームで暮らしていたぼくも、孤独死する可能性があったはずだ。ぼくの死はフロアを満たし、そこに住まう人々は「死後10日経ってたらしいよ」と顔をしかめていたかもしれない――。
そんな具合に、本書『孤独死のリアル』は、孤独な「死」が、容赦なく社会に「漏れ始めて」おり、自分もまたその当事者になりかねないことを感じさせてくれます。
本書でもっとも印象的なのは「死はもはや個人・家族の私的な事柄ではなく、公的な事柄として扱わなければいけない」という指摘です。地縁が希薄化していく現代社会において、死は、ときに腐敗臭を伴うグロテスクなかたちで、隣家から漏れ出てくるのです。
私たちはどのようにして、社会化する死と向き合っていけばよいのでしょう。介護の実務と政策に精通した著者は、多数の具体的な事例とともに、解決策を提示しています。「なんとかしないといけない」という著者の切実な筆致に、ぐいぐいと引き込まれます。
本書『孤独死のリアル』を手に取ると、自分がどう暮らし、どう死にたいのかを、否が応でも考えることになります。死生観を問い直す1冊としても、あなたに影響を与えてくれるでしょう。