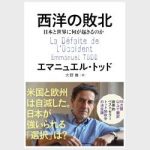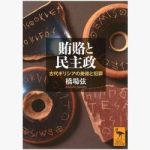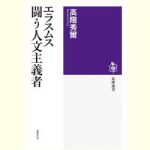不平等が生み出す社会の分断
本書『平等について、いま話したいこと』は、欧米を代表する2人の知性が「平等」を巡って交わした白熱の議論を編集してまとめたものだ。
一方の著者トマ・ピケティは、フランスの経済学者でパリ経済大学の教授を務める。著書『21世紀の資本』は700ページを超える大著であるにもかかわらず、日本でもベストセラ―となり話題を呼んだ。
もう一方の著者マイケル・サンデルは、アメリカのハーバード大学の教授を務め、対話形式の授業の模様がテレビ番組『ハーバード白熱教室』として放送されたこともあり、日本でもっともよく知られている政治哲学者のひとりである。
出自も思想的立場も異なる二人が行った対話なので、平等な社会の実現に関する議論には対立点がある。しかし、不平等がもつ問題点に関しては驚くほど意見が一致している。
両者によれば現在世界に蔓延する不平等には、3つの側面があるという。機会の不平等、政治的不平等、尊厳の不平等である。
そして、こうした問題の背景には現在の資本主義の在り方と、それを当然のことと思い込ませる能力主義というイデオロギーがあるという。 続きを読む