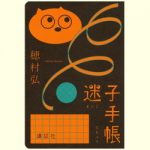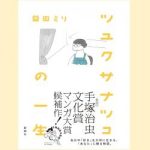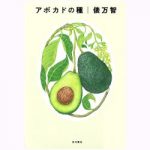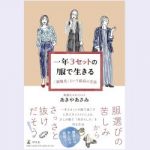10代のころから日記をつけている。といっても、永井荷風のように戦争中は戦火で焼かれないように風呂敷包みにして避難するほど大切にしたわけではない。「欺かざるの記」と称して、文学青年風の日記をつけて、少しばかり気取っていたのだ。
高校の入学祝いに、親しい友人から梶井基次郎の全集を贈られて、彼の日記を毎日読んだ。梶井は30歳で亡くなっているのだが、商業誌に書いたことがほとんどなく、作品を発表する媒体はたいてい同人誌だった。けれど、生活は作家そのものだった。
僕はそれに憧れて、梶井の日記を読んで、作家の生活をまねた。確か、太宰治の『人間失格』に、上京して大学の友人から教わったのは、酒と煙草と女とマルキシズムだった、というようなことを書いていた気がするが、僕は梶井の日記から、文学者の在りようを学んだ。
日記はおもしろい。日本文学には古くから日記文学の伝統があるけれど、文学者だけでなく、市井の人の書いたものでも、そこに人の暮らしや、時代の空気があって、興味を惹かれる。
坪内祐三の『日記から 50人、50の「その時」』は、小説家、詩人、学者、政治家、官僚、レーサーなど、さまざまな人物の日記から構成されている。もっともいちばん多いのは文学者だけれど、作家は日記をつけるのが仕事にもなるのだから自然なことだろう。 続きを読む