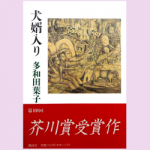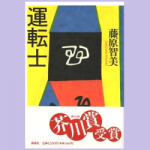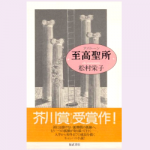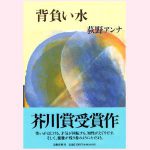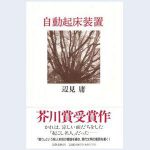独特の文体で、奇妙でリアルな世界を描き出す
多和田葉子著/第108回芥川賞受賞作(1992年下半期)
引き込まれる独特の文体
第108回芥川賞を受賞した多和田葉子は、「村上春樹よりもノーベル賞に近い」とも言われる作家だ。実際、2016年にはドイツの文学賞「クライスト賞」を受賞し、2018年には米国で最も権威のある文学賞のひとつとされる「全米図書賞」を受賞している。国内でも、2000年に「泉鏡花文学賞」、2003年に「伊藤整文学賞」と「谷崎潤一郎賞」、2011年に「野間文芸賞」、2013年に「読売文学賞」を受賞し、2020年には「紫綬褒章」を受章している。
そんな彼女が32歳の時に芥川賞を受賞した作品が「犬婿入り」だ。『群像』(1992年12月号)に掲載された77枚の短編である。 続きを読む