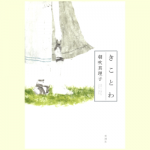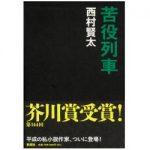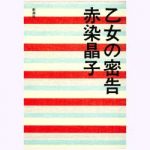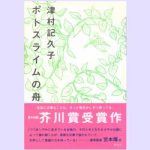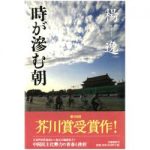記憶を行き来する中で霞む存在の危うさ
朝吹真理子(あさぶき・まりこ)著/第144回芥川賞受賞作(2010年下半期)
多くの選考委員がその才能を評価
前回取り上げた「苦役列車」とダブル受賞となったのが、朝吹真理子の「きことわ」だった。当時26歳。詩人で慶応大学教授の朝吹亮二の娘であり、フランソワーズ・サガンの翻訳を多く手がけた朝吹登水子を大叔母に持つという、いわばサラブレッドということもあって、受賞前から多くの関心を集めたようである。実際、選考会では少しの難点を指摘する声を除いて、多くの選考委員がその才能を高く評価している。
主人公は永遠子(とわこ)と貴子(きこ)。初めての出会いは永遠子が15歳、貴子が8歳。貴子の両親が所有する葉山の別荘を管理していたのが逗子に住む永遠子の母親。その関係で、毎年夏になると2人は、その別荘でまるで本当の姉妹のように遊ぶのだった。
やがて、貴子の家族が別荘に来ることがなくなって以降、2人は会うことも連絡を取り合うこともなくなり、再会したのが、その別荘を取り壊すことになった25年後のこと。永遠子も貴子もすでに大人になっていた。 続きを読む