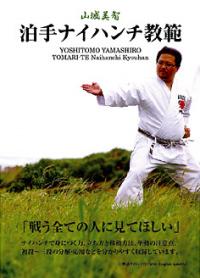歴史ある剛柔流の常設道場

4階建てビルの最上階が伝統ある明武舘の道場。入り口はビル1階の左にある(那覇市久米)
沖縄初の空手流派として知られる剛柔流の創始者・宮城長順(みやぎ・ちょうじゅん 1888-1953)の戦前からの古い弟子であった八木明徳(やぎ・めいとく 1912-2003)が開いたのが明武舘(めいぶかん、正式名称・国際明武舘剛柔流空手道連盟総本部)だ。
戦後、焼け野原から復興がスタートした那覇市久米に、71平米の木造平屋建ての道場が建設された。久米は歴史的には中国の明から派遣された「閩人(びんじん)三十六姓」(久米三十六姓)の居留地となった場所で、後の久米村をつくった。これらの人々は琉球の国づくりに貢献したことで知られる。
八木明徳の一代記『男・明徳の人生劇場』(2000年)によると、明徳は戦後、コザ警察署などに勤務したあと、那覇に戻ったのは1949年4月のことだった。法務局の登記簿によると、八木道場の土地は1953年1月、建物は1958年3月に八木明徳によって所有権保存がなされている。ふつうに考えて58年以前にも建物があったはずだが、いつ道場が開設されたか、正確に日付を特定することは難しい。戦後、長嶺道場や比嘉道場(究道館)ができたころとさほど変わらない時期と推測される。 続きを読む