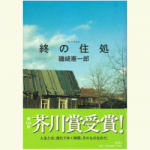寄る辺のない不穏な空気
磯﨑憲一郎(いそざき・けんいちろう)著/第141回芥川賞受賞作(2009年上半期)
挑戦的な作風
磯﨑憲一郎の「終の住処」。2度目の芥川賞候補で受賞。当時44歳。
小説は、何をどのように書いても自由なわけだが、ある程度の作法というものはあるはずだ。そうしたものを壊して新たな作法で書くことは、小説の新たなおもしろさを開く可能性を秘めている反面、失敗すれば理解不能にもなりかねない。「終の住処」は、そうした挑戦的な試みに満ちているような印象を受けた。
まず、時間軸が長い。結婚をして、子供が生まれて、何人もの女性と不倫を重ね、家を建てて、老いを目前にするまでの長い人生の時間を、わずか原稿用紙110枚程度で描いている。一貫して流れているのは、家族、なかんずく妻という他人との理解しがたい境である。
また、そこで起きるさまざまな出来事には連続性がない。AがあったからBがあってCとなるといった、因果関係に基づいた連続性がないので、個々の出来事が全く無関係な無機質な独立した出来事のように見えるのだ。 続きを読む