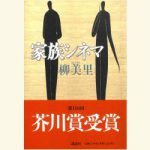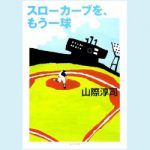映画という虚構の中で、家族の実像を浮かび上がらせた
柳美里(ゆうみり)著/116回芥川賞受賞作(1996年下半期)
舞台を観ているような展開
第116回の芥川賞は2作品が受賞。柳美里の「家族シネマ」と辻仁成の「海峡の光」だ。いつも手厳しい石原慎太郎もこう述べている。
箸にも棒にもかからぬような候補作とつき合わされる不幸をかこつこともままあるが、今回はどの作品も一応は読ませてくれた
今回はまず柳美里の「家族シネマ」を取り上げる。受賞時は28歳。27歳の時にすでに「フルハウス」と「もやし」でそれぞれ113回と114回の芥川賞候補となっている。また、「フルハウス」は第24回泉鏡花文学賞と第18回野間文芸新人賞を受賞していて、その実力は折り紙付きだった。 続きを読む