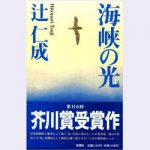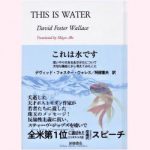いじめの被害者と加害者の未来。人間の不可解な本性に迫る
辻仁成(つじ・ひとなり)著/第116回芥川賞受賞作(1996年下半期)
ロックバンド「ECHOES」のヴォーカル
第116回の芥川賞はダブル受賞となった。ひとつは前回取り上げた柳美里の「家族シネマ」。もうひとつが今回取り上げる辻仁成の「海峡の光」だ。
辻仁成は、もともとロックバンド「ECHOES」のヴォーカルだった。1985年にミュージシャンとしてデビューして、そのわずか4年後に第13回すばる文学賞(受賞作「ピアニシモ」)で作家としてもデビューしているから、多彩な才能と言わざるをえない。当時は、有名ロックバンドのヴォーカルだから文学賞をもらえたのではないかというひねた見方をする者も一部にいたようだが、芥川賞受賞作「海峡の光」を読めば、それはひどい偏見だったことが分かる。 続きを読む