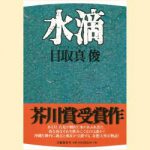衆院選に続く2党の大敗
7月10日に投開票がおこなわれた第26回参議院選挙は、与党の圧勝で終わった。
自民党は単独で改選議席125の過半数となる63議席を獲得。公明党も選挙区7候補が激戦を制して全員当選を果たし、13議席を獲得した。
一方の野党は、立憲民主党が改選23議席から大きく後退して17議席にとどまり、日本共産党も6議席から4議席へと大敗した。
立憲民主党は獲得議席数では辛うじて野党第一党の座を保ったものの、比例区の得票数では日本維新の会に及ばなかった。日本維新の会は改選議席の6から12議席へ倍増させている。
さらに立憲民主党は、参議院幹事長だった現職の森裕子氏が自民党の新人に敗北。小沢一郎氏のおひざ元である岩手選挙区でも、現職の木戸口英司氏が自民党の新人に敗北し、1992年以来30年ぶりに自民党が勝利した。
また比例区でも、有田芳生氏や白眞勲氏といった現職が議席を失った。 続きを読む