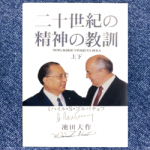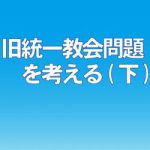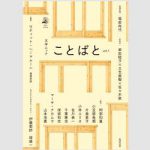世界基準から遅れている日本
SDGs(持続可能な開発目標)は、17項目のうち5番目として「ジェンダー平等を実現しよう」を掲げている。またSDGsの全体を貫く「誰も置き去りにしない」という理念は、LGBTQ(性的マイノリティ)の権利があらゆる場面ですべての人々と平等に尊重されるべきことを示している。
今や大学では「ジェンダー」「LGBTQ」に関する講座が人気を集めており、企業や自治体も関連する研修に余念がない。
すべてのEU加盟国、米国、オーストラリアといった先進国では、既にLGBTQ差別を禁じる法律が整備されており、この流れはグローバルスタンダードになりつつある。一方、日本にはこうした法制度がいまだ存在しないままだ。 続きを読む