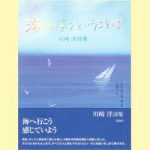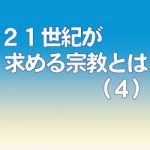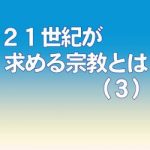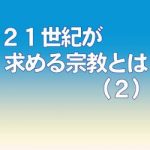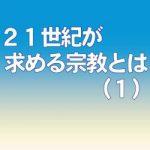さまざまな言葉がある。信仰の言葉は生死の軸になる。人を救う言葉だ。哲学の言葉は世界を探求するために役立つ。人を聡明にする言葉だ。では、文学の言葉は、どうか? 分かりやすい言い方をすれば、人の心を表現するから、人間を知ることができる。そして、生きるための知恵を与えてくれる言葉だ。
僕は小説家なので、小説書くために、ほかの小説家の書いた小説を読む。これはマーケティングだ。どのような小説が書かれていて、どのような小説が書かれていないか、知っているといないとでは、大いに自分の書く小説が違ってくる。
誰もが書いている主題や物語や人物など書いても、おもしろくない。誰も書いていないものを見つけなければ、小説家として生き残ることはできないのだ。そこがビジネスの世界と文学・芸術が違うところだ。
どれだけ村上春樹が読まれていても、世界に村上春樹は2人もいらない。1人で十分だ。大学やネットの通信講座で小説の書き方を教えていると、必ず、その時期に流行している小説に似た作品を書いてくる人がいる。
最初から小説の書き方が分かる人はいない。だから、自分が好きな小説家の真似をする。それは仕方のないことだ。ただ、世に出て行く人と、足踏みをしている人の差は、その先にある。 続きを読む