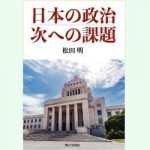立憲民主党・岡田幹事長
ウクライナ大使館が異例の抗議
支持率の低迷、党内の不協和音が続く立憲民主党執行部に、新たな〝悩みのタネ〟が出てきた。
9月14日、立憲民主党は岡田克也幹事長が同党の原口一博衆議院議員を口頭注意したと発表した。
原口氏は1959年生まれ。東京大学卒業。佐賀県議会議員(自民党所属)を経て1996年に衆議院議員(新進党)。1998年に民主党に合流し、2009年に民主党政権が発足すると総務大臣に就任した。
2012年には民主党代表選に立候補するも落選。民進党を経て2018年、国民民主党の代表代行。2020年に立憲民主党に参加。2023年4月、悪性リンパ腫であることを公表した。6月の国会質問で「がんが消えた」と発表している。
さて問題となったのは、9月12日にYouTubeで配信された番組内での原口議員の発言だった。原口議員はウクライナをめぐって「日本はネオナチ政権の後ろにいる」などと発言した。 続きを読む