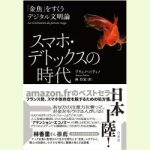スマートフォンに閉じ込められた「金魚」
スマホを巡る問題を扱った書籍は数多く出版されている。医学的視点から書かれたものが多い中、本書『スマホ・デトックスの時代』はそうした見地を踏まえた上で、IT企業の収益システムや社会的な問題をも視野に入れて議論を展開している。
冒頭で紹介されるIT企業幹部が行うプレゼンテーションの内容は衝撃的だ。金魚は金魚鉢のなかを飽きることなく泳ぎ回る。記憶力と集中力がごくわずかしか持続しないため、つねに新しい場所を泳いでいると勘違いしているからだ。某IT企業はデジタル技術を駆使した研究によって、金魚の集中力が持続する時間をつきとめた。その時間はわずかに8秒未満。8秒を過ぎるとすぐに精神がリセットされるのだという。
さらに、同社は生まれた時からスマホなどのデジタル機器に取り囲まれて育ったミレニアム世代の注意持続時間の算定にも成功した。その時間は金魚よりわずかに1秒長い9秒だ。9秒を過ぎると彼らの脳の働きが低下するので、新たに刺激的な通知や広告を提供する必要がある。そのために同社は、これまで収集した個人データを活用して、彼らの関心を呼び起こそうとしているのだという。 続きを読む