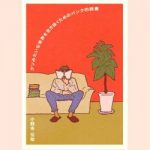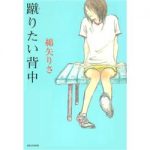創価学会の誕生と核兵器の出現
――池田名誉会長の逝去に対しては、ICAN(核兵器廃絶キャンペーン)のメリッサ・パーク事務局長からも弔意が寄せられました。事務局長は、さる1月23日にも総本部を訪問し原田会長と会見しています。ICANは核兵器禁止条約の発効を実現させ、2017年にはノーベル平和賞を受賞していますね。
青山樹人 池田先生の大きな足跡の一つとして、核兵器の廃絶と核軍縮へ向けた〝民衆の側からの世界世論〟を喚起したことが挙げられると思います。
第二次世界大戦中の1943年7月、初代会長の牧口常三郎先生と、理事長でのちに第2代会長となる戸田城聖先生は、不敬罪と治安維持法違反容疑で軍部政府に逮捕され投獄されました。
軍部政府は戦争への総動員体制を推し進めるため、国民に国家神道を強制し、事業所や各家庭にも伊勢神宮の神札(神宮大麻)の奉掲などを命じていました。両先生は日蓮仏法の正義に基づいて神札を拒み、それが不敬罪・治安維持法違反に問われたのです。両先生は「信教の自由」を貫いて逮捕・投獄されました。
取り調べに対しても牧口先生が堂々と信念を語っていたことは、『特高月報』にも記録されています。高齢だった牧口先生は、1944年11月18日に老衰のため獄死されました。戸田先生は獄中で法華経の精読と唱題を重ね、〝仏とは生命なり〟と覚知し〝われ地涌の菩薩なり〟との自覚に立ちます。
戸田先生が豊多摩刑務所から出所されたのは、1945年7月3日のことです。既に深く心に期するものがおありだったのでしょう。出所直後に名前を「城聖」と改めています。 続きを読む