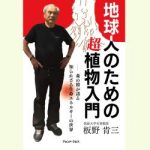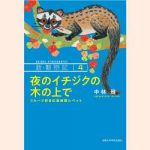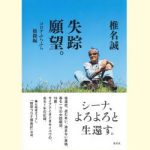木と話すそうだ。木とは樹木の木である。大丈夫か? とおもった人は少なくないだろう。僕も、そうだった。特にプロローグの、明治神宮にいる樫の木のスダジイとのやりとりは、これは……と感じた。
あるとき著者がスダジイに、そこでなにをしているのか尋ねたら、すごいエネルギーが返ってきたのだという。しかも、人間についての辛口な批評がふくまれたメッセージとともに。
そこからスダジイのモノローグがつづく(これは著者がうけとった植物の思いを言葉に翻訳したものだ)。スダジイが言うには、日本にはいくつか国の錨(アンカー)になる場所があって、植物たちはそこへ地球の強い生命エネルギーを流すことで、自然のバランスを保っている。
しかし人間はバランスを崩すようなことをする。つりあいを失ったところは蝕まれて、人間や動物が病むこともある。実は、人間も地球の生命エネルギーの場にいるのだが、それを意識することができず、地球の生命エネルギーに同調する力を失っている――。
などなどとメッセージを伝えてくるのは、「木の魂の中でも、大元の魂」。そして、地球上の植物はすべてが大元の魂とつながっている。木にもいのちが宿っているのだ、という。 続きを読む