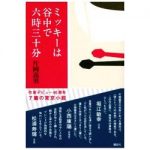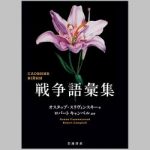気になる作家がいて、一度作品を読んでみようとおもうのだけれど、なかなか手に取る機会がない。いや、機会はつくるものだから、手に取るまでの関心が動かないというべきだろうか。
では、その作家が嫌いなのかと訊かれると、読んでないのだから応えようがない。やはり、手に取る機会がない、としかいいようがないのだ。そういう作家のひとりが、僕にとっては片岡義男だった。
『スローなブギにしてくれ』で野生時代新人賞をもらってデビューした作家ということぐらいしか知らなかった。この小説を原作にした映画もTVのロードショーで観た。映画は率直にいって、あまりおもしろいとはおもわなかった。
いつもの僕なら原作を取り寄せて比べてみるぐらいのことはしただろう。けれど、このときは、そうしなかった。なぜだかは分からない。それからもう30年近い歳月が流れている。
そして、最近になって、発作的に片岡義男の小説本を買った。『ミッキーは谷中で六時三十分』だ。これは明らかにタイトル買いだった。見た瞬間に、買わなければ、とおもった。 続きを読む