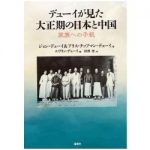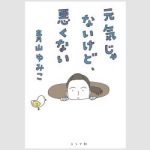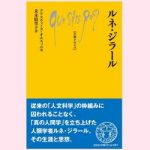日本の軍国主義に警鐘を鳴らす
ジョン・デューイは20世紀前半のアメリカを代表する哲学者ある。また日本とは深いつながりがあり、第二次世界大戦後に制定された日本国憲法の不戦条項や民主主義化には彼の考え方が強く反映されている。いわば日本で生まれ育ったすべての人が関わりを持つ人物でもある。
本書は、日本と中国を旅行したデューイとその妻アリス・チップマンが米国にいる子供たちへ書き送った手紙をまとめたものだ。1919年1月から6月まで、日本発27通、中国発37通が収録されている。デューイの著作は難解で読みにくいといわれているが、本書は両国を訪問した際の印象が率直に綴られていて、とても読みやすい。これまで彼の著作を読んで挫折した人こそ、ぜひ手に取ってほしいと思う。 続きを読む