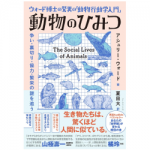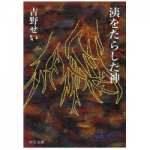身内から「バカ」と言われた立憲
参議院で審議が続いている政治資金規正法改正案。
自民党の一部派閥議員による政治資金収支報告書不記載に端を発したこの問題。自民党だけでなく多くの野党でも横行していた、領収書なしの「使いきり」で党から議員に渡される政策活動費など、国民感覚から大きくズレた〝政治とカネ〟が浮き彫りになった。
政治が国民からの信頼を失えば、政策遂行ができなくなる。失われた信頼を取り戻す最重要課題は「再発防止」、つまりこのような事案を起こさせない制度作りだ。
この問題にもっとも早く反応したのは与党・公明党だった。公明党は1966年に共和グループから自民党と社会党への献金を暴露し、衆議院解散(黒い霧解散)に追い込むなど、結党当初から〝政治とカネ〟の問題にはどの政党よりも厳しく追及してきた歴史がある。
今回も、1月半ばには各党に先がけて「透明性の強化」「罰則の強化」など具体案を盛り込んだ「公明党政治改革ビジョン」を発表。4月には事実上の党独自案となる「政治資金規正法改正案の要綱」を発表して、同じ与党である自民党にも独自案の提出を迫った(公明党「公明党政治改革ビジョン」2024年1月18日発表)。
一方、残念だったのは立憲民主党をはじめとする主要野党が、最初からこの問題を「政局化」しようと図り、実現する見込みのない提案を並べてパフォーマンス合戦に終始したことだった。 続きを読む