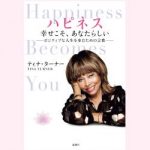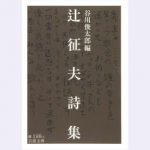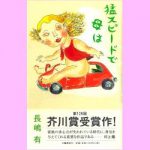「日本からなくなったらいい政党」
7月23日、インターネット番組に出演した日本維新の会の馬場伸幸代表は、日本共産党について、「言ってることが世の中ではあり得ない、空想の世界を作ることを真剣にマジメに考えている」「日本からなくなったらいい政党」などと発言した。
日本共産党が党綱領で「社会主義・共産主義の社会」をめざしていることを指していると思われるが、共産党側は猛反発し、発言の撤回を要求した。
だが馬場代表は26日、「謝罪や撤回するという気は全くない」と述べた。
馬場氏はその上で、共産について「公安調査庁から破防法(破壊活動防止法)による調査団体に指定されている。破防法による調査対象団体ということは、危険な政党であるというふうに、政府としてみているということだ」と述べた。(「朝日新聞デジタル」7月26日)
事実、公安調査庁のサイトには、「共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解」が掲載されている。 続きを読む