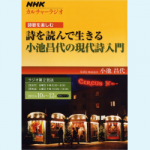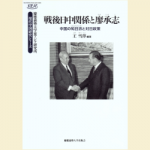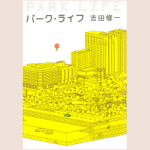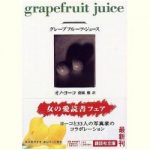かつてこのコラムで『百冊で耕す』という本をとりあげた。そのなかで、こんなことを書いた。なかなか読書の時間がとれないとこぼす人がいる。すきま時間で読めばいい。
すきま時間で同時並行に読む――偏食ならぬ偏読にならないよう、①海外文学、②日本文学、③社会科学か自然科学、④詩集、を15分ずつ読むというのは、参考になった(WEB第三文明 連載エッセー「本の楽園」 第163回 百冊で耕す)
これは、いまも続けていて、なかなかいい習慣になっている。今回は詩の本について書きたい。
『詩歌を楽しむ 詩を読んで生きる 小池昌代の現代詩入門』は、NHKで放送された現代詩入門の講座をまとめたムック本だ。小池昌代は、詩と小説の両方を書く作家として知ってはいた。けれど、まとまった著作を読む機会がなかった。
古書店をパトロールしていたら、この本を見つけた。ぱらぱらとめくってみると、おもしろそうだ。ためらわず買うことにした。
ちょっと脱線するが、本も人と同じで出会うタイミングがある。古書店や新刊書の書店で本を手にして買うかどうするか迷う。こういうときは、買いである。そうでないと、やっぱりほしいとおもって出向いても、すでになくなっていることがある。
僕は何度か後悔した。それで、迷ったら買い、という原則をつくった。それから後悔はない。ただ、仕事部屋の本が増えるので、妻から小言をいわれることが増えたけれど、小説家の妻なのだから、そこは我慢してください。 続きを読む