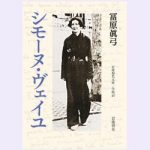吉村知事の〝部下〟だった斎藤知事
「大阪以外で初めて誕生した維新系知事」だった斎藤元彦・兵庫県知事。元総務官僚だった斎藤知事は、総務省時代の2018年から大阪府に出向し、府の財務部財政課長をつとめていた。
吉村大阪府知事とは、いわば〝上司と部下〟の関係。2021年7月の兵庫県知事選挙で、日本維新の会は自民党と共に斎藤氏を推薦し、選挙戦では大阪市長であった松井一郎氏(当時の日本維新の会代表)、大阪府知事の吉村洋文副代表らが兵庫県下に乗り込んで熱烈に支援した。
だが、その斎藤知事は今や、無所属議員まで含めた県議会の全会派の全議員から「辞職」を求められている。
斎藤知事が内部告発した元局長を調査結果も待たずに処分した問題で百条委員会が設置されても、日本維新の会の馬場代表は静観の姿勢を崩さなかった。
しかし、8月の箕面市長選挙で維新所属の現職が惨敗すると、8月31日になって藤田文武幹事長が兵庫維新の会幹部や県議団と協議に入った。世論の読み間違いというよりも、維新に蔓延する〝驕り〟〝ガバナンスの欠如〟のあらわれであろう。 続きを読む