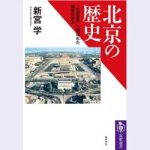第31回 方便②
[2]二十五方便の出典と思想的意義
二十五方便が何に基づいて形成されたかということに関して、『摩訶止観』巻第四上には、「此の五法の三科は『大論』に出で、一種は『禅経』に出で、一は是れ諸の禅師の立つるなり」(第三文明選書『摩訶止観』(Ⅱ)、372頁)と述べている(※1)。
呵五欲(色・声・香・昧・触の五種の対境に対する欲望を呵責すること)、棄五蓋(貪欲・瞋恚・睡眠・掉悔・疑の五種の煩悩を捨てること)、行五法(欲・精進・念・巧慧・一心の五法を実行すること)の三科は、『大智度輪』巻第十七(大正25、181上~185中を参照)に基づいて立てられたものである。具五縁(持戒清浄・衣食具足・閑居静処・息諸縁務・得善知識)の一科は、『禅経』に基づくと述べられているが、この『禅経』が具体的に何という経典であるかは不明である。関口氏は、「天台大師は、ひろくこれらの諸経論(禅秘要法経、坐禅三昧経、禅法要解、小道地経、大般涅槃経、止観門論頌、菩提資糧論など――菅野注)に注意し、主としては禅経類により、あわせて遺教経、成実論などをもちいつつ、呵五欲、棄五蓋、行五法に対応させて、五項目から成る具五縁なるものを新たに構成したのであろう」(※2、『天台止観の研究』105頁)と述べている。 続きを読む