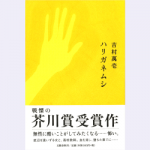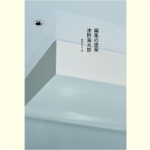暴力性の生まれる暗部の構造を描く
吉村萬壱(よしむら・まんいち)著/第129回芥川賞受賞作(2003年上半期)
不気味な寄生虫「ハリガネムシ」
第129回の芥川賞受賞作は、『文学界』に掲載された吉村萬壱の「ハリガネムシ」だった。
受賞作のタイトルにもなっているハリガネムシについて、作中では詳細には解説されてはいないが、調べてみると実に薄気味悪い生物だ。くねくねと動く細長いひものような寄生虫で、乾燥すると針金のように硬くなることが名前の由来らしい。本来は水生生物で、カゲロウなどの水生昆虫に捕食されそれをカマキリなどの陸上生物が捕食すると、その陸上生物に寄生し成長を続ける。最終的には、ある種の神経伝達物質を使ってカマキリを酩酊状態にし、川などに入水させた後にカマキリの尻からにゅるにゅると出て行って水の中へと帰っていく。この作品の不気味さをうまく象徴しているタイトルである。
平凡な教師だった主人公の〈私〉が堕落・変質していくきっかけとなったのは、ソープ嬢のサチコと出会いだった。社会の底辺を這いつくばるように生きてきたサチコとの交流の中で、自らの中にある肉欲を含む暴力性に徐々に目覚めていく様は、実に見事でありスリリングでもある。 続きを読む