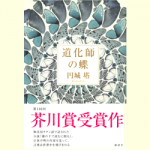難解な作品に対する期待
円城塔(えんじょう・とう)著/第146回芥川賞受賞作(2011年下半期)
選考委員も「分からない」
本コラムでは、これまでも読むのが難儀な分かりづらい幾作品かの芥川賞作品を扱ってきたが、これほどまでに難しい作品は初めてだった。円城塔の「道化師の蝶」である。愚鈍な私の未熟な読解力ゆえの結果かと思いきや、『文藝春秋』(2012年3月号)の「芥川賞選評」を読んでみると、多くの選考委員が「分からない」と述べているではないか。少々、安堵。
少し長くなるが、そのまま選考委員の選評を引用する。
まずは黒井千次。
作品の中にはいって行くのが誠に難しい作品だった。出来事の関係や人物の動きを追おうとするとたちまち拒まれる。部分を肥大化させる読み方に傾きかけると、それもまたすぐ退けられる。つまり、読むことが難しい作品であり、素手でこれを扱うのは危険だという警戒心が働く