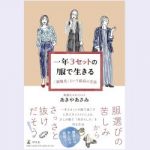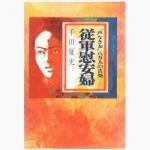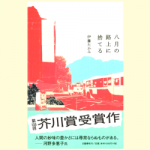このあいだ衣替えをしていた妻が、いきなり仕事部屋のドアを開けて、いらない服はすてます、といった。ちょっと待ってよ。置いてあるんだから、全部いるでしょ。でもさ、もう5年も着てない服があるわよ。それだけ着なかったら、もう、いらないでしょ。
5年のあいだ着ていない服は捨てる――これは妻が実行している5年ルールらしい。結婚して30年以上になるけれど、初めて知った。彼女はそうして持ち物を整理しているのだ。
でも、5年のあいだ着ていなくても、突然に着ようとおもうことだってあるかもしれない。そんなこといってるから、どんどん服が溜まっちゃうのよ。じゃ、自分でやってね。その日から僕は捨てられない人の烙印を押された。
確かに妻のいうことも一理はある。仕事部屋を見ても、僕は書類がなかなか捨てられない。本は増えてゆくばかり。いつか、資料として使うかもしれない、とおもうからだ。やはり僕は、捨てられない人なのか。
そんなことを考えながら本屋をぶらぶらパトロールしていたら、『一年3セットの服で生きる』という本を見つけた。 続きを読む