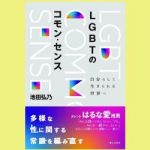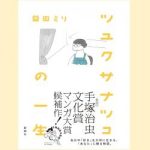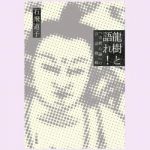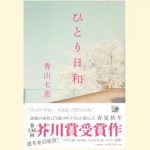誰もが自分らしく生きるために
著者の池田弘乃氏は、ジェンダーやセクシュアリティ、フェミニズム法理論などの研究を進める気鋭の法哲学者。現在は山形大学で教授を務めている。
新著『LGBTのコモン・センス』では、著者はこれまでも取り組んできた性的マイノリティの権利保障の問題について、当事者への丹念な取材を通して、日本社会における制度的な不備や、社会に根づく誤解や偏見などを浮かび上がらせ、性に対する私たちの常識(コモン・センス)を編み直していく。
今私たちが性に対して〝常識〟と考えているそれは、単に時代の制約を受けたものであったり、漠然とした印象によるものでしかなかったりするのではないか。そうした〝常識〟が、人々に「男らしさ」や「女らしさ」を過剰に押しつけ、一人ひとりが「自分らしく」生きることを阻害しているのではないか。
著者はこうした問題意識のもと、読者とともに性についての常識の編み直しを図る。そして、多様な性のあり方を確認しながら、誰もが「個人として尊重」される社会を展望していく。 続きを読む