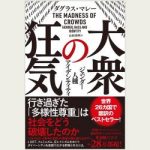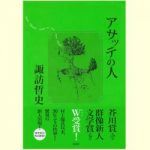分断と対立を乗り越える日本の役割
79回目の「原爆の日」を迎えた8月6日、広島平和記念公園での平和祈念式典に参列した公明党の山口那津男代表は、そのあと広島市内で記者会見に臨んだ。
席上、山口代表は明2025年が「被爆80年」「戦後80年」の節目を迎えることを踏まえ、公明党として「平和創出ビジョン」の策定に入ることを発表した。
公明党の山口那津男代表は6日、広島市内での記者会見で、2025年に戦後80年の節目を迎えるのを受けて党の「平和創出ビジョン」を策定すると発表した。核廃絶、気候変動、人工知能(AI)などを柱にまとめる。
党内に検討委員会を設置し、来春までに内容を詰める。検討委の委員長には谷合正明参院議員が就く。山口氏は「分断を乗り越える日本の役割を推し進める原動力になりたい」と述べた。(『日本経済新聞』8月6日)