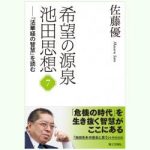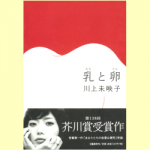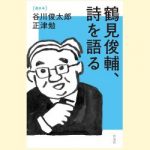国家指導者を「悪魔化」する危険
作家であり日本基督教団に属するプロテスタント信徒である著者が、池田大作・創価学会第3代会長の主著の1つ『法華経の智慧』を読み解くシリーズ。月刊誌『第三文明』に連載中のものを単行本化した第7巻目となる。
内容的には『法華経の智慧』の「如来神力品」後半部分にあたるのだが、とりわけ本書に収録された連載期間(2022年8月号~2023年7月号、2024年2月号・3月号)にはいくつもの重要な出来事があった。
まず、新型コロナウイルスによるパンデミックが終息していない時期であり(WHOによる終息宣言は2023年5月5日)、ロシアによるウクライナ侵攻が2022年2月に始まって、まだ半年という時期であった。
周知のように著者は元・外務省主任分析官であり、在職中はモスクワの日本大使館にも勤務していた。旧ソ連崩壊直前にゴルバチョフ大統領(当時)がクーデター派によって誘拐監禁された際、その生存情報を西側世界で最初にキャッチして東京に伝えたのが著者だった。 続きを読む