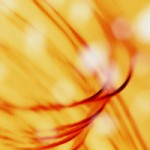オープンリー・ゲイ(※注)のタレントの活躍
民放のバラエティー番組で「オネメン」を紹介するコーナーがあった。オネメンというのは、〝オネエ系イケメン〟の略語らしい。
「外見は女性を大いに魅了するのに、残念ながら彼らが女性の愛に応えることはない」という女性目線からの設定だ。
登場する男性は、男っぽい表情でカメラを睨んだあと、しなを作りながら高い声の〝オネエ言葉〟で喋ってギャップを見せ、会場の笑いを誘う。もちろん、番組の演出上そういうふうに指示されていたのだろう。
※注 オープンリー・ゲイ: 同性愛者であることを公表した人々
少し前のほんの一時期、バラエティー番組の世界を中心に「オネエ系」と称される人々がブームのように持て囃された。だが、テレビ的に消費され尽くすと露出も一気に減り、現時点で生き残ったのはマツコ・デラックスに代表される「女装系」の人々になった。
一貫しているのは、オネエ系であれ女装の人々であれオネメンであれ、彼らは主に女性の支持によって視聴率に貢献し、社会の中で認知を得ていることである。
この国がマイノリティーに対して以前より寛容になったことには異論がないとしても、きわめて大きくなった女性マーケットの力学が、あくまで特定のタイプに限定して(しかも基本的には女性ではなく男性の同性愛者に限定して)彼らを承認し賞揚しているに過ぎないのだと思う。
それでも、こうした状況によってオープンリー・ゲイが昼夜を問わずテレビ画面に登場し、そのことによってLGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーといった性的マイノリティー)全般が社会の中で可視化されてきた面があることの意味は大きい。
つまり、社会の中に存在しているにもかかわらず公然と扱われないということは、それらの人々が存在しないことにされている、もしくは存在は知られているが公正に扱うに値しない人々だと、暗黙のうちに了解されていることになるからだ。
反面、視聴率を意識した演出が主導していくことで、同性愛者といえば女装を好み、あるいはしなを作ってオネエ言葉で喋る男性という、きわめてテレビ的でステレオタイプな像がすっかり拡散されてしまっている。
そうした特定のデフォルメされたイメージだけが社会に定着し、「可視化された」と思い込まれていくことで、大多数のLGBTの人々がかえって可視化されることのないまま、引き続き〝存在しないも同然の人々〟として放置されてしまうのであれば元も子もないのではないか。
実際、今ではオープンリー・ゲイのタレントを抜きにしてバラエティー番組が成り立たないほど彼らの存在が日常の光景になっている一方で、たとえば同性婚に関して、日本では議論どころか話題にすらならない現状がある。
宗教的背景もあり、かつてはホモフォビック(同性愛嫌悪)が吹き荒れた欧米や豪州の土地では、同性婚を異性婚と同等に扱おうとする社会的変化が確実に進んでいる(表1)。
これらの国々では同性のパートナーの存在を公表している首相や閣僚、行政の首長も珍しくない。
聖書が同性愛を禁じているとして同性愛に対して最も保守的な牙城であったバチカンも時代の変化を受け止め、この7月には教皇フランシスコが「同性愛行為は罪だが、私に同性愛者の司祭を裁く資格はないし、彼らを隅に追いやるべきではない」と、歴史的ともいえる発言をおこなった。
本年6月、米国の連邦最高裁判所は、同性婚を異性婚と差別していた結婚防衛法を、法の下に自由や財産権の平等を認めた連邦憲法修正5条に違反すると判決した。
同性婚の認否そのものについては各州の州法にゆだねながらも、連邦としてこれまで異性婚には認められながら同性婚には認められてこなかった税制や相続の優遇など1000を超す権利が、同性婚にも平等に適用されるべきだと判断された。
これは、単に同性婚の当事者のみならず、同性カップルのもとで育てられている子供たちにも、ようやく平等をもたらすものとなった。
読み違えてならないのは、こうした欧米社会を中心とした世界の変化は、「差別されてきた特殊な人々に平等な権利が与えられた」のではなく、性というパーソナルな問題を理由に他者の人権を不当に奪ってきた自分たちの社会の欠陥に、人々が気づき、その是正を始めたということなのだ。
言い換えれば、同性婚という世界の今日的な潮流にまったくと言っていいほど関心を示さない日本社会は、同じ土地に暮らす他者の人権を奪っている自分たちの歪んだ姿を、依然として自覚していないのである。
黙殺されてきた「社会の欠陥」
本年のゲイ・プライド週間にちなんでFacebookが実施した調査では、米国のFacebookユーザーのじつに7割が「LGBTを公表している友だちがいる」と回答している。
さまざまな統計から、日本でも少なくとも人口の5%がLGBTだと推計されているという。すなわち友人や知人が計20人以上いるという人(たいていの人がそれに該当するはずだ)は、ほぼ100%の確率でその友人・知人の中にLGBTの人がいることになる。
テレビの中では毎日のようにLGBTを見ながら、自分の人間関係にはそんな人がいないというのであれば、それは存在していないのではなく、身近な誰かが人並みの権利を奪われたまま声も出せずに生きているということであり、自分がそれに気づいていないだけということなのだ。
同性婚というLGBTをめぐる象徴的なイシューは、かつての黒人差別撤廃になぞらえて「21世紀の公民権運動」とも称されている。
繰り返すが、それはあの元都知事が発言して非難を浴びたような「気の毒な」「何かが欠けている」人々の身の上の問題なのではない。
あえてこの愚かな発言になぞらえれば、身近に生きている他者の人権を不当に抑圧し奪ってきた「気の毒な」「何かが欠けている」自分たちの姿を、自覚できるのかできないのかという、社会の側に突き付けられた問題なのである。
異性愛者には自明のように認められている人間としての諸権利が、同性愛者とその子どもからは剥奪されているというのは、「法の下の平等」「基本的人権の尊重」を謳った憲法とも相容れない。
さて、それでもこうしたことがらに対して切迫したリアリティーを抱くことが難しい日本社会で、誰が、どのように、風穴を開けていけるのだろうか。
これが、黙殺されてきた「社会の欠陥」である以上、たとえば人権や福祉の政策に地道に取り組んできたような比較的若手の政治家には、同じように新しい価値観や感性を共有できる若い世代の有権者たちを議論に巻き込みながら、是非リーダーシップをとってもらいたいと思う。
あるいは、性愛が人間の内心に根差す根源的なテーマであることを踏まえるならば、宗教者ないしは宗教運動に携わる青年たち――とりわけ平和や人権の問題を考えてきたような人々――にも、21世紀の重要な人権問題としての認識を新たにしてもらいたい。
LGBTの人権が置かれている状況が、その国、その社会の、人権意識のメルクマール(指標)といわれていることの意味を、よくよく噛みしめていきたいのである。
(表1) ※2013年8月時点
同性婚を認めている国や地域
【ヨーロッパ】オランダ、ベルギー、スペイン、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、デンマーク、フランス、イギリス
【アメリカ大陸】アルゼンチン、カナダ、ウルグアイ、ブラジル、メキシコ、アメリカ合衆国のうちワシントンD.C.と13の州
【アフリカ】南アフリカ共和国
【オセアニア】ニュージーランドパートナーシップ法がある国や地域
【ヨーロッパ】ノルウェー、スウェーデン、グリーンランド、フランス、ドイツ、フィンランド、イギリス、ルクセンブルク、イタリア、アンドラ、スロベニア、スイス、チェコ、アイルランド
【アメリカ大陸】アメリカ合衆国の6つの州、メキシコシティ、コアウイラ州(メキシコ)、ブラジル、ウルグアイ
【オセアニア】ニュージーランド、タスマニア州(オーストラリア)、オーストラリア首都特別地域