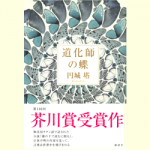難解な作品に対する期待
円城塔(えんじょう・とう)著/第146回芥川賞受賞作(2011年下半期)
選考委員も「分からない」
本コラムでは、これまでも読むのが難儀な分かりづらい幾作品かの芥川賞作品を扱ってきたが、これほどまでに難しい作品は初めてだった。円城塔の「道化師の蝶」である。愚鈍な私の未熟な読解力ゆえの結果かと思いきや、『文藝春秋』(2012年3月号)の「芥川賞選評」を読んでみると、多くの選考委員が「分からない」と述べているではないか。少々、安堵。
少し長くなるが、そのまま選考委員の選評を引用する。
まずは黒井千次。
作品の中にはいって行くのが誠に難しい作品だった。出来事の関係や人物の動きを追おうとするとたちまち拒まれる。部分を肥大化させる読み方に傾きかけると、それもまたすぐ退けられる。つまり、読むことが難しい作品であり、素手でこれを扱うのは危険だという警戒心が働く
続いて髙樹のぶ子。
一見いや一読したぐらいでは何も確定させないぞ、という意思を、文学的な志だと受け取るには、私の体質は違いすぎる。それが『位相』の企みであると判ってはいるが、このような努力と工夫の上に何を伝えたいのかが、私には解らない
宮本輝は、
これは小説になっていないという意見もあれば、読んだ人たちの多くが二度と芥川賞作品を手に取らなくなるだろうとまで言う委員もいた
と賛否が分かれた選考会の裏側を伝えている。また、選考委員の中から出てきた、この作品の意図するところを紹介しながら、
だとすれば、円城さんの『道化師の蝶』は、作者の『眼は高い』が『手は低すぎる』ということになる
と述べている。志の高いものを創り出そうとしてはしているが、技術がそれに達していない、というのだ。
さて、どういう作品なのか。自分でも分からないのだから、解説のしようもないのだが、そういう意味では作品に対して無礼なことを承知の上であえて紹介すると、ざっとこんな感じだろうか。
扱っているのは、おそらく、言葉のもつ不確かさを浮き彫りにする言語論。そして、発想とはどこからどのようにして生まれてくるのかという発想論。国籍不明の友幸友幸(ともゆきともゆき)という多言語作家が残した膨大な原稿(言葉)を巡って、幾人かの「わたし」が登場し、彼や彼が残したものの正体に迫ろうとする。
言えることはたったのこれだけだ。それでもなぜこの作品が芥川賞を受賞したのか。それはある種の期待であろう。文章は、極めて端正なのに、構築しようとしているものは意味不明。もし、これがひどい文章ならば、駄作の一言で切り捨てられるだろうが、乱れのない確かな文章であるがゆえに、伝えようとしているものがきっと最後には見えてくるはずだと期待してしまうのである。ところがそういうふうにはならないのだが、ならば、それはそれで次の期待が膨らんでくる。つまり、分からないものを手にした時に、「(再読して)自分こそがこの謎を解き明かしてやる」という、自尊心を土台とした探究心をくすぐるのである。
この点について、髙樹のぶ子はこう述べる
伝えるためではなく、言葉で構築した世界に、読者を迷い込ませるのが目的であるなら、根気強い読者には根気強く彷徨って貰えるだろう。得心できるより、得心できないものに快を感じる読者もいるだろうが、それは私ではない。にも拘わらず最後に受賞に一票を投じたのは、この候補作を支持する委員を、とりあえず信じたからだ。決して断じて、この作品を理解したからではない
新たな文学を切り開いたか
では、この作品を支持した委員は何を支持したのか。
まず黒井千次。
芥川賞は小説としての完成度のみを競うのではなく、多様な可能性に向けて出発する足場を提供するものなのだろうから、時としてある選者の理解が及ばぬ作品が受賞作と決まってもおかしくはない
次に川上弘美。
日常の言葉では語り難いことを、どうにか日常の言葉で語ろうとしつづけているこの作者の作品は、読むことも大変に困難です。けれど、それでもあえてその難儀な試みを続ける作者に、芥川賞が与えられたこと。それは、私にとって大変喜ばしいことでした
最後に島田雅彦。
こういう「やり過ぎ」を歓迎する度量がなければ、日本文学には身辺雑記とエンタメしか残らない
結局、宮本輝がいう眼の高さ、新たな文学を切り開こうとする態度が、その確かな文章力を背景として評価されたようである。
今回を最後に選考委員を退いた石原慎太郎は、最後まで厳しい言葉を投げてきた。
こうした言葉の綾とりみたいなできの悪いゲームに付き合わされる読者は気の毒というよりほかない。(中略)故にも老兵は消えていくのみ。さらば芥川賞
受賞インタビューで石原慎太郎の選評に食いついたのが、W受賞となったもう一人の受賞者、田中慎弥であった。その受賞作「共喰い」については次回取り上げる。
「芥川賞を読む」:
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』 第4回『妊娠カレンダー』 第5回『自動起床装置』 第6回『背負い水』 第7回『至高聖所(アバトーン)』 第8回『運転士』 第9回『犬婿入り』 第10回『寂寥郊野』 第11回『石の来歴』 第12回『タイムスリップ・コンビナート』 第13回『おでるでく』 第14回『この人の閾(いき)』 第15回『豚の報い』 第16回 『蛇を踏む』 第17回『家族シネマ』 第18回『海峡の光』 第19回『水滴』 第20回『ゲルマニウムの夜』 第21回『ブエノスアイレス午前零時』 第22回『日蝕』 第23回『蔭の棲みか』 第24回『夏の約束』 第25回『きれぎれ』 第26回『花腐し』 第27回『聖水』 第28回『熊の敷石』 第29回『中陰の花』 第30回『猛スピードで母は』 第31回『パーク・ライフ』 第32回『しょっぱいドライブ』 第33回『ハリガネムシ』 第34回『蛇にピアス』 第35回『蹴りたい背中』 第36回『介護入門』 第37回『グランドフィナーレ』 第38回 『土の中の子供』 第39回『沖で待つ』 第40回『八月の路上に捨てる』 第41回『ひとり日和』 第42回『アサッテの人』 第43回『乳と卵』 第44回『時が滲む朝』 第45回『ポトスライムの舟』 第46回『終の住処』 第47回『乙女の密告』 第48回『苦役列車』 第49回『きことわ』 第50回『道化師の蝶』