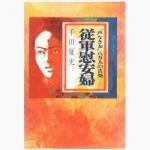吉田証言の問題点と慰安婦の真相は別のもの
今から10年前の2014年8月5日と6日の2日間にわたり、朝日新聞は、従軍慰安婦問題に関する吉田清治(よしだ・せいじ 1913-2000)証言を扱った過去の記事を取消し、訂正する特集を掲載した。慰安婦問題に批判的であった第2次安倍政権時代のことであり、朝日新聞を一斉に批判する風潮が右派メディアを中心に強まった。
その前年頃から、一部メディアは、慰安婦問題に関する総括的な謝罪表明ともいえる「河野官房長官談話」(1993年8月)の信ぴょう性を疑う主張を強め、慰安婦問題でこれ以上日本政府が責任を追及されるいわれはない、との主張を繰り返した。
朝日新聞が吉田清治証言を取り消したことで、右派側は慰安婦の強制連行(いわゆる「慰安婦狩り」)の裏づけも丸ごと無くなったかのように勢いづき、もはや慰安婦問題は終わったかのごとき主張を繰り返した。
しかし、この問題を全体の文脈で振り返れば、吉田清治の主張や証言は、従軍慰安婦問題に関して、実際はほとんど重きをなしていないものだ。
吉田は1983年に出した『私の戦争犯罪 朝鮮人強制連行』(三一書房)において、戦時下の過去に吉田自身が済州島に出向き、慰安婦にするため200人以上の現地女性を狩り出す作業に従事したと書いたが、その内容の裏付けがとれないとして問題視されてきたことは事実だ。
最終的に朝日新聞が記者を派遣して現地の70代後半から90代の「40人に話を聞いたが、強制連行したという吉田氏の記述を裏づける証言は得られなかった」(2014年8月5日付朝日新聞)。これらの調査を行ったのは、すでに70年を過ぎた段階であり、「慰安婦狩り」があったかなかったか、その存在を特定するには年数が経ちすぎていた。
そもそも吉田証言は、慰安婦に関する多くの論評や告発の中では、時期的には「後発」に位置する。それ以前に小説やノンフィクションの形で発表された多くの作品があった。有名なのは、直木賞作家の伊藤桂一(いとう・けいいち 1917-2016)や元毎日新聞記者の千田夏光(せんだ・かこう 1924-2000)のものだ。
伊藤は実際に軍隊経験をもち、千田はぎりぎりで徴兵を免れることのできた年代だった。今回は、ジャーナリストの視点と手法で慰安婦問題を最初に作品化した人物である千田夏光を取り上げたい。
千田作品の骨格は間違っていない
千田夏光がベストセラーで超ロングセラーとなった書籍『従軍慰安婦 〝声なき女〟8万人の告発』(双葉社)を発刊したのは1973年10月。私が所持している同書は、同年12月に発行されたもので、わずか2カ月で「20版」となっている。翌年には続編の『続・従軍慰安婦 償われざる8万人の慟哭』も刊行され、これも1カ月で「7版」を数える売れ行きとなった。
2つの書は正続合わせて55万部が出版された。内訳は正篇35万部、続篇20万部(『週刊ポスト』1992年3月13日号)で、千田の回想によると、「正・続合わせて50余万部売れましたが、ほとんど反響はありませんでした」(『論座』1999年9月号)という。
2冊は1976年に、内容を1冊にまとめ『従軍慰安婦悲史』(エルム)として出版され、さらに1978年に改訂新版(三一新書)となり、つづいて1984年には講談社文庫に引き継がれ、長く読まれた。
千田の本は戦時下、日本軍兵士を慰める目的で開設された「慰安所」で働いた女性たち(いわゆる「慰安婦」)に、従軍記者や従軍看護婦と同じく「従軍」の名を冠した最初の本となったことでも有名だ。
「慰安婦」の前に「従軍」の文字を付けるのは適切ではないとの意見があるが、「慰安婦」が当時の日本軍に付随して組織された女性であった事実は疑いようがない。「適切ではない」との指摘は、感情レベルのものとも言えよう。
私がこれらの千田作品を重視するのは、彼が新聞記者の取材経験と手法を踏まえ、この問題の当事者たちに広く取材し、可能な限り全体を俯瞰した上で執筆したからである。
千田によると、「足かけ8年間の取材のすえ」(『あの戦争は終ったか』1978年)に2冊を書いたと記している。そのため取材そのものは戦後20年ほどすぎた60年代半ばに着手されたことがわかる。当時はまだ戦争を体験した人たちが多く生き残っていた時代だ。
千田夏光の書いた雑誌記事として、「週刊新潮」(1970年6月27日号)に掲載された「特別レポート 日本陸軍慰安婦」というタイトルの13ページの記事がある。
この「新潮レポート」には元衛生将校(軍医)で戦後、福岡市内で産婦人科医として開業した麻生徹男(あそう・てつお 1910-1989)が登場する。1973年に発刊された千田の最初の書籍でも、中心人物として登場するキーパーソンの一人だ。日中戦争が始まった翌年の1938年、慰安婦開設のための「第1号の検診医」になったとされる人物である。
「新潮レポート」では中国の満州国境に駐屯した同じ福岡県出身の部隊で、3000人の兵隊に30数人の慰安婦が存在した中、生きて日本に戻ることができた日本人慰安婦8人と兵隊らが戦後も戦友会を開き、人間関係が続いている逸話が登場する。
戦中の〝疑似夫婦〟の関係を、戦後に生き残った男たちが感謝とともに懐かしみ、その後の女性たちの人生を温かく見守るという話だった。だがこれらの特殊なエピソードとは対照的に、朝鮮人慰安婦の置かれた境遇は悲惨なものが多かった。
対照的な朝鮮人慰安婦の立場
日本軍は終戦時、慰安婦に関するすべての資料を一斉廃棄したため、慰安婦の総数はいまも確かなことがわかっていない。千田が2冊の書籍の副題で提示した「8万人」という数字は、全兵士の数に対する比率計算からはじき出されたそれなりに信ぴょう性のある数字と受けとめることができる。
「新潮レポート」にも登場するが、慰安婦は「大半が朝鮮人」だったと指摘されている。さらに日本女性は「もとめて行った」人が多かったのに対し、朝鮮女性は「狩り出されていった」という決定的な違いがあった。日本女性の場合はほとんどが玄人だったが、朝鮮人女性の多くは一般女性で、男性経験をもたない未婚の10代が中心だった。逆にそのほうが性病の心配もなく、日本軍にとっては都合がよかったともいえる。彼女たちは中国大陸や南方など日本軍が展開していたすべての地域に分布し、働かされた。
慰安婦の中でも特に朝鮮人慰安婦が問題とされるようになったのは、普通の農村の10代の女性たちを、工場で働けるとか兵隊たちを元気づける仕事だなどと〝騙して〟連れて行ったことに尽きる。逆にいえば、本当のことを告げたら、人数を集められなかったことが明らかだった。彼女たちは日本軍の戦争継続のためにかき集められた〝道具〟にすぎなかった。
結果的に、詐欺の手口に引っかかり、1日何十人もの男を慰安するための「共同便所」の立場に堕とされた事実は重い。処理する人数など通常の売春婦とも仕事の形態は明らかに異なっていた。酷使を余儀なくされた彼女たちの若い肉体は子どもを産めない身体となり、貞操観念の強かった当時の朝鮮半島ではまともに結婚することもできず、恥ずかしくて故郷に戻れないケースも多かった。
前出の衛生将校・麻生徹男の二女で、父親と同じように産婦人科医として福岡県で仕事をした女性は、千田の一連の作品について、「正篇に63カ所、続篇には23カ所問題のある記述があります」と否定的に書き残す。今となっては、90年代初頭の慰安婦問題の関心の集まりと、マスコミによる取材ラッシュに辟易したことが明らかだが、その女性が千田作品で誤りと主張した骨子を確認してみると次のようなものだ。
①従軍と慰安婦を結んで造語をしたこと
②根拠なしに強制連行と結びつけたこと
③娼婦連れで戦った唯一の軍隊として品位を落としたこと(※旧日本軍以外の諸外国にも同様のシステムがあったとする趣旨)
④麻生軍医(※女性の父親)が朝鮮人慰安婦強制連行の責任者のようにほのめかしたこと
結論するに、これらの批判は千田作品の根幹となる部分の真実性を否定する内容となっているわけではない。細かな箇所に事実誤認の要素があったとしても、話の骨格は取材に基づく事実と考えるべきだろう。
ただし②の「強制連行」については、その後も多くの史料が発見され、朝鮮においても「強制連行」同様の事案に当局が手を焼いたことはすでに明らかになっている。つまり、そうした事案が発生していたとの結論になる。
同じ日本人として旧日本軍の戦争遂行を支え、自分たちの将来を台無しにすることを余儀なくされた数万人規模の女性たち。その多くは現地で命を落とし、運良く帰国できたとしても、戦後は長らくその存在を省みられることすらなかった。正式な軍籍があったわけではなく、日本政府による恩給や補償の対象にすらならなかった。そればかりか慰霊塔の一つすら立てられなかった事実は重い。これらの女性のほとんどがすでに鬼籍に入った。だが彼女たちが生きた歴史の真実が消え去ったわけでは決してない。(文中敬称略)
「反戦」「従軍慰安婦」関連:
「嫌中嫌韓」ブームを読み解く(2014年)
「反知性主義」の風潮を憂う~慰安婦問題・南京事件めぐって(2015年)
「反戦出版」書評シリーズ① 『男たちのヒロシマ――ついに沈黙は破られた』
「反戦出版」書評シリーズ② 『語りつぐナガサキ――原爆投下から70年の夏』
「反戦出版」書評シリーズ③ 『未来につなぐ平和のウムイ』
「反戦出版」書評シリーズ④ 『家族から見た「8・6」 語り継ぎたい10の証言』
「ジャーナリズム」関連記事:
書評『ジャーナリストの条件 時代を超える10の原則』
連載エッセー「本の楽園」 第172回 パレスチナ
書評『ニュースの未来』――石戸諭の抱く「希望」とは
書評『歪んだ正義』――誰もがテロリストになり得る
書評『コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か』
日本再生の力は成熟したインターネット文化にある