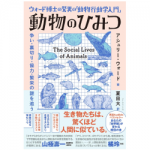「社会的動物」は人間以外にも存在する
古代ギリシャの哲人アリストテレスは、人間と他の動物を隔てる特徴は社会生活にあると考え、「人間は社会的動物である」と定義した。しかし動物の研究が進むにしたがい、他の動物も社会的であることが分かってくる。特にこの半世紀は観測技術が向上し、生態の解明が急速に進んだ。さらに動物たちは言葉はもたないが、声や分泌物、身振りなどを使い、複雑なコミュニケーションを行っていることも明らかになった。
本書『動物のひみつ』は社会的動物研究の第一人者が、近年の研究成果を一般の読者に分かりやすく紹介したものである。
本文だけで約700ページあるが、明快でユーモアに溢れた筆致で綴られており、読む人を飽きさせない。
このような協力行動は、「社会的動物」の特徴の一つだ。(中略)最も基礎的なレベルの協力は、「社会的緩衝作用」と呼ばれている。
これは、オキアミから人間にいたるまで、あらゆる社会的動物が、ただ同種の動物のそばにいて関わり合うことだけで確実に生じる利益のことだ。社会的動物は、単に集団でいるだけで、集団によって支えられるのである。(本書7ページ)
動物はなぜ社会をつくるだろうか。著者は、単独で成しえない多くのことが可能になるからだと考える。簡単にいえば、その方が〝得〟ということだ。
多くの動物は、集団を作ることによって危険から身を守る。その規模が大きいほど、捕食者から逃げられる確率は格段に上がるという。
また情報の共有により、効率的にエサを得ることができる。ある研究者は、アリの群れを巣からエサまでの経路が32768通りある迷路のなかに置くという実験をした。すると、わずか1時間で最短経路を発見してしまったという。こうした研究はコンピュータサイエンスの分野にも取り入れられ、町の交通網の作成やセールスマンの効率的な巡回ルートの割り出しにも応用されている。
同じアリでも分類的にはゴキブリに近いシロアリは、高度な社会性を持つ昆虫である。防衛、子育てなど、集団のなかでそれぞれが役割を担う。驚くべきなのは両親が同じでも、担当によって外見まで違うことだ。さらにシロアリは蟻塚を作ることでも有名だが、大きいもので9メートル、体の1000倍もある。意外にも人間以外の動物で複雑で巨大な建築を築くのは、社会性のある昆虫だけであるという。この点も極めて興味深い。
集団になり暴走する場合も
ただ、一種だけ、人類の多くに壊滅的な被害をもたらす恐れがあるにもかかわらず、ほぼ対抗手段がない、という動物がいる。(中略)その動物とはバッタである。この昆虫は、何十億という数が群れを成し、休むことなく長い距離を移動し続け、通った場所のほぼすべてを破壊し尽くす。(本書59ページ~60ページ)
集団を作ることで悪影響を受ける動物もいる。ある種のバッタはふだん単独で暮らし、性格もおとなしい。しかし一旦、集団を作り始めると狂暴化する。広範囲に移動しながらあらゆるものを食い尽くし、人間にも自然環境にも破壊的な被害をもたらす。なぜ豹変するのか。
その秘密は後肢(昆虫の後ろ足)にあった。ある研究者が5分おきに絵筆でバッタの後肢を撫で続けるという実験をした。すると約4時間後、バッタが変化した。体の色が変わり、性格も狂暴化した。干ばつなどが起こると草むらが減り、バッタは密集する。そのとき他のバッタの頭があたるのが後肢なのだ。エサがないので、ふだんは食べないものでも食べるようになり、共食いを始まる。前進しなければ仲間に食べられてしまう。バッタの集団移動は、恐怖が生み出す狂気の行進だったのである。
社会的動物としての人間
このように人とのリアルタイムの関わりが減る一方で、ヴァーチャルな関わりは増えている。/「それが何か問題なのか?」という人もいるだろう。私は問題だと考える。私たち人間はあくまでも社会的な存在だからだ。私たちの人生は、友人、愛する人たちのネットワークと相互に密接に結びついている。一人一人が、広い社会の中で常に何らかの役割を果たしている。(本書8ページ)
社会的動物が相互に影響を与えあう点も興味深い。
動物の個体差はDNAによりほぼ決まっていると考えている人も多いのではないだろうか。しかし遺伝子の発現の仕方は、周囲の環境、なかんずく他者との関係に影響される。DNAが約4割で、環境やその他の要因が約6割だという。
ネズミは子供の頃に母親や他の個体との関係が良好でないと、周囲とコミュニケーションが不得手になり、危険な病気になる確率も上がってしまう。
シャチは海の王者といわれるが、意外にも群れを統率するのは年老いた雌である。この雌が死亡すると、その集団の死亡率は一気に跳ね上がる。死亡後1年のデータを見ると雌は5倍、雄はなんと14倍に達するという。
こうした事例は、社会的動物が他者から受ける影響の大きさを物語っている。
著者は人間もまた社会的動物であることを忘れてはならないと繰り返し強調する。
現在、パソコンやスマホの画面の前で1日の大半を費やしている人が数多く存在する。しかし友人や家族との親密な人間関係から得られるものは、想像以上に多い。さまざまな知的発見や人格的触発を得られるだけでなく、健康にも良い影響を与える。
また、どんな人でも生きている限り、社会を通じて他の人に影響を与えているという視点も見逃せない。人間関係が苦手で、友人も少ないと悩む人も多い。しかし本書で紹介されている研究によると、人間が社会的交流をできる数の上限はネズミと同じ12人である。またネズミの社会では1匹が利他的行動をとると、共感からその行動が伝染するように広がるという。
ここから目の前にいる身近な人を大事にしていくことの方が、派手な人脈を誇ることよりも、はるかに重要だということが理解できる。人間にとっても善いことは目の前の1人から広まっていくのである。
本書を読み進めると、どの社会的動物の生態もじつに興味深く、また解明されていない謎が存在していることが良くわかる。さらに数多く存在する社会的動物のなかでも、人間ほど謎に満ちた存在はいないことにも気づかされる。
社会的動物の驚きに満ちた生態は、知れば知るほど興味がわいてく。それは人間を理解すること、ひいては自己を知ることに通じているからであろう。
『ウォード博士の驚異の「動物行動学入門」 動物のひみつ 争い・裏切り・協力・繁栄の謎を追う』
(アシュリー・ウォード著/夏目大訳/ダイヤモンド社/2024年3月26日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧