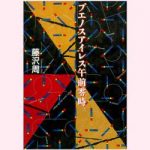目の見えない老婆の踊るダンスに浮かびあがる輝きと寂寥感
藤沢周(ふじさわ・しゅう)著/第119回芥川賞受賞作(1998年上半期)
W受賞となった第119回芥川賞受賞作の一つは、藤沢周の「ブエノスアイレス午前零時」だった。それまでの藤沢周は、「ゲルマニウムの夜」の作者・花村萬月と共通する荒々しい力が持ち味だと思っていたが、本作品は、以前芥川賞候補となった3作品とは異なる静謐な空気を漂わせている。
――主人公のカザマは、東京を離れて雪深い故郷に戻り、冴えない温泉宿の従業員として働いていた。朝、源泉で温泉卵を作ることから始まる退屈な日々に埋没する生活を送っていた――。
カザマが、なぜ故郷に戻ってきたのか、東京で何があったのか、詳しいことは何も書かれていない。しかし、何らかの挫折を経験して都落ちのようにして戻ってきたことは、情景描写や会話の中で徐々に浮き上がってくる。経歴的なことは書かずに読み手に暗に伝えることのできる巧みな筆力だ。
希望も刺激もない鬱々とした日々が続くのだが、それが大きく転換するのが老婆の登場からだ。
――都会からやってきた中高年の社交ダンスグループの中に、盲目で、しかもかなり進んだ認知症と思われる老婆がいた。若いころは横浜で外人相手の娼婦をしていたという噂のある老婆だった。
この宿の唯一の自慢は、ダンスフロアが併設されていることで、従業員はみな仕事として客のダンスの相手をする。成り行き上、カザマは、この老婆のダンスの相手をすることとなる――。
物語の展開としてはたったこれだけなのだが、ラストシーンを読み合えた後の驚きと切なさは、これこそが小説の持つ力だと思わざるをえない鮮やかなものだった。カザマが抱えてきた過去の輝きと今を対比した際に感じる侘しさや過去への憧憬が、老婆の抱えていた同質ものと交錯し共鳴し、深い寂寥感が漂うのである。老婆は、今は記憶も薄れ、目も見えないけれども、かつては輝く日々があり、その追憶の背景に漂う寂寥感が胸を打つのだ。
タイトルの「ブエノスアイレス午前零時」も見事だ。おそらく、これは、この老婆の記憶だ。彼女がかつて愛し愛されたのかもしれない男のいる遠い国、アルゼンチン。カザマに手を取られ忘我の境地で踊る老婆のダンスは、ひなびた温泉宿のダンスホールなどではなく、タンゴが響き渡るブエノスアイレスの真夜中の豪華なダンスホールなのだろう。
技法的には、輝いていた昔の時をフラッシュバックさせながら、冴えない今という瞬間の中に過去の輝きを描きだし、深い寂寥感を醸し出している。そして、二人の内面に深入りすることなく、遠目に描きながら的確にその内面を描くその筆力は、鮮やかというしかない。
選考委員の黒井千次はこう評価する。
その仄暗い光の下に漂い出すのは、何かが通り過ぎて行ってしまった後の、うら寂しい現代の風景である。しかしそこには、まだ狂ったように走る光の点や、掌に掬われた温かな空気の感触もしっかり書き留められている
一方、厳しい評価をした選考委員もいた。宮本輝はこう述べる。
藤沢氏の作品には、いつも、材料を上手にまとめただけといった印象を持つ。「書かれた小説世界」以上の何かが、読後、湧き上がってこない
日野啓三はこう述べる。
適当な記号的イメージを適当に並べて感傷的に味つけした中間風俗小説
田久保英夫はこう述べる。
こうした二つの世界を、フラッシュバックさせながら進む描写はあざやかだ。それは最後の男と老女が踊る情景にも、よく現れている。ただ、これまでの作品を見ても、どんな題材も巧みに書けそうで、私はそこに貫くつよい内的なモティーフを感得したい、と思う
つまり、筆力は巧みなのだが、描こうとするものの志の低さのようなものを指摘しているのだろうか。〝純文学〟の登竜門の最高賞である芥川賞の難しさである。その後、作者は人気作家として活躍しているわけで、評価というものの難しさを感じざるをえない。
「芥川賞を読む」:
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』 第4回『妊娠カレンダー』 第5回『自動起床装置』 第6回『背負い水』 第7回『至高聖所(アバトーン)』 第8回『運転士』 第9回『犬婿入り』 第10回『寂寥郊野』 第11回『石の来歴』 第12回『タイムスリップ・コンビナート』 第13回『おでるでく』 第14回『この人の閾(いき)』 第15回『豚の報い』 第16回 『蛇を踏む』 第17回『家族シネマ』 第18回『海峡の光』 第19回『水滴』 第20回『ゲルマニウムの夜』 第21回『ブエノスアイレス午前零時』 第22回『日蝕』