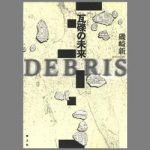子供のころ、いくつか憧れた仕事があった。まず、船乗りと建築家だ。広い海に出て世界をめぐるのは、何とも愉快な仕事におもえた。それから自分の好きなように道路を引き、橋を架け、ビルを建てるのも、同じように愉快におもえた。
ところが、僕にはできないと分かった。僕には、色弱という生まれつきの眼の異常がある。赤や黄色やはっきりとした色の見分けはつくのだが、微妙な色の違いがわからないのだ。
船乗りは通信に手旗信号を使う。その色の見分けがつかないといけない。建築家は電気の配線などを指示する。やはり、その色の見分けがつかないといけない。僕にはそれができないのである。
このことを知ったとき、子供なりにショックだった。母親に不満を述べた。そうしたら、彼女は、ふん、と鼻先で笑って、産んでもらっただけありがたいとおもえ、とうそぶいた。僕は驚いて言葉を失った。
早くに連れ合いを亡くして、酒場でママさんと呼ばれる仕事をしながら、女手一つで2人の子供を育てた人物は、そんなことで同情したり、産んだ自分を責めたりする繊細な母親ではなかった。豪傑だった。
僕は船乗りも建築家も諦めた。特に船乗りにはまったく興味がなくなった。しかし建築家は、ずっと気になる存在だった。
『瓦礫の未来』の著者である磯崎新は、2019年度のプリツカー賞(建築界のノーベル賞といわれているらしい)を受けた建築家だ。20世紀のなかばごろから、建築界だけでなく、この国の文化全般の領域で少なからぬ影響を与えてきた。
磯崎は、世界に名高い建築家らしく地球をめぐる。ただ、そのなかでも辺境に関心を寄せる。
「ポスト・コロニアル」以後(ポスト)になって、環球的な事件は辺境にこそ発生すると考えた
環球とは、地球全体を意味する。つまり、辺境で起きていることを知れば、世界の変容を知ることができるというわけだ。
第2章の「クルディスタン」を見てみよう。磯崎は、イラクから亡命しているアーティストに出会った。フセイン政権に追われているらしい。ところがその政権が倒れた。新たな政権で大統領になった人物とは、ともに山中に隠れていたと一緒に撮った写真を見せた。
彼の依頼は、
われわれのために現代美術館をつくって欲しいんだ
ということだった。「われわれ」とは誰のことなのか? 磯崎たちはイスタンブールに向かった。そこを経由して北部イラクの小都市アルビルに着いた。さらにキルクークに案内される。ここは、当時まだ内戦中の地域だったが、油田地帯なので制圧できれば、オイルマネーが入ってくる。
豪華な現代美術館だって何だって建設できるよ。クルド国家の美術館だ。
どうやら「われわれ」とは、クルド人たちのグループらしい。彼らは独自の国家を建てようとしているのだ。磯崎は、ある商店の入り口に見慣れない国旗を見つけた。イラク国旗に似ているが、違う。店のなかには「クルディスタン」の地図があった。イラン・イラク・シリア・トルコにまたがった大きな領域が国境線で囲まれている。
それはクルド人が主権国家を樹立したときのクルド国家の地図である。入り口にあったのは、その国旗だったのだ。国家を持たないクルド人たちは民兵を組織し、各地でパルチザン活動をしながら、国家の樹立をめざし、まず、「神殿」としての美術館を建てようとしていたのだ。
この逸話だけでも十分に、「環球的な事件」を知ることができる。
話はクルド人の居留地になっているアララット山に及ぶ。この地には、「方舟伝説」がある。ノアの箱舟から世界に残された大洪水神話が語られ、中国は黄河の治水から中華文明が生まれたという流れになる。
磯崎は、また日本の古代に思いを凝らし、中国の安仁鎮に飛んで当地の現代美術をめぐる状況を語り、北朝鮮の「主体思想」に言及する。そして、随所に見られるのは、建築家としてデビューしてからの仕事を通じて、1968年で近代が終わったという確認である。
世界の、特に辺境をめぐりながら、「環球的な事件」のなかに身を置き、僕らがこれから依り代(しろ)としていくことのできる何物かを探る。
あらためて組み立てるべきシステムは混沌(荘子)であると私は考える。これが維持されるのは、その内部でイムニタス(免疫)が作動するときである。これを明確に定義した方式はまだない。
この書物も混沌である。しかしそれは磯崎新の思考によってコントロールされている。この混沌ぶりは心地いいし、そこから新しい何物かが生じる予感に満ちている。
おすすめの本:
『瓦礫の未来』(磯崎新/青土社)