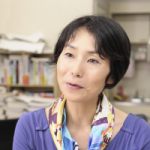「カード」「保険」「住宅」――20代、30代のライフ・プランニングを考える
お金を稼ぐことは社会貢献
若い方からお金に関する相談を受けるとき、私はお金の価値をポジティブに認めることの大切さをお話ししています。世の中にはお金はなんとなく汚いものであり、お金に興味を抱くことが、何かはしたないことであるかのようなイメージがあります。しかしお金は、私たちが商品やサービスという「価値」を社会に提供することで得られた正当な対価です。つまり「たくさんお金を稼ぐ人」は、世の中にたくさんの価値を創造し、大きな社会貢献をしていると考えることもできるのです。 続きを読む