第77回 正修止観章㊲
[3]「2. 広く解す」㉟
(9)十乗観法を明かす㉔
⑥破法遍(5)
(4)従仮入空の破法遍④
④空観(2)
次に、絶言を破ることについて、絶言は四句(自生・他生・共生・無因生)の外に出るといっても、十種の四句があるので、どの四句の外に出るのかと問い詰めている。 続きを読む

⑥破法遍(5)
(4)従仮入空の破法遍④
④空観(2)
次に、絶言を破ることについて、絶言は四句(自生・他生・共生・無因生)の外に出るといっても、十種の四句があるので、どの四句の外に出るのかと問い詰めている。 続きを読む
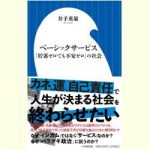
現在、高い関心を集めている社会保障政策に「ベーシックサービス」がある。教育、医療、介護、障がい者福祉などのサービスを、全ての人に無償で提供するというものである。
本書『ベーシックサービス:「貯蓄ゼロでも不安ゼロ」の社会』は、提唱者の慶應義塾大学経済学部教授の井手英策氏によって書かれた入門書である。2021年に刊行した『どうせ社会は変えられないなんて誰がいった』(小学館)を大幅に加筆訂正したものだ。
読者一人ひとりに語りかけるような文章で綴られているが、実証的なデータをふまえるだけでなく、歴史学や社会哲学などの成果を幅広く取り入れた議論が展開されているので、本書を読み進めればベーシックサービスだけでなく、我が国の社会保障政策に対する理解も確実に深まる。政治や社会保障に少しでも興味がある社会人や学生にはぜひ手にしてほしい一冊である。 続きを読む

3連休の中日であった2月23日午後7時半から、神戸市内で記者会見がおこなわれた。
こわばった表情で報道陣の前に現れたのは、日本維新の会・岩谷良平幹事長(衆議院議員)、東徹(衆議院議員)、兵庫維新の会・金子道仁代表(参議院議員)の3氏。
冒頭、岩谷幹事長は次のように述べた。
今般、わが党の県会議員にさまざまな報道がなされております。まず増山県議に関しまして、ルールを軽視した極めて不適切な行動があったと認識をしております。そして岸口県議に関しましては、百条委員会副委員長としての自覚に欠けた行動があったというように認識を致しております。
日本維新の会として、これらのことに関しまして、心から深くお詫びを申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。(【動画】「THE PAGE(ザ・ページ)」2月23日)
こう言い終わると、日本維新の会の3氏は深々と頭を下げた。
岩谷幹事長が言及した「わが党の県会議員」とは、いずれも兵庫維新の会に所属する兵庫県議会議員、岸口実、増山誠、白井孝明の3氏のこと。党幹事長が謝罪会見に臨むほどの不祥事。いったい、この3人は何をしでかしたのか。 続きを読む

⑥破法遍(4)
(4)従仮入空の破法遍③
今回は、十乗観法の第四「破法遍」の続きである。破法遍の段落のうち、これまでに「広く破法遍を明かす」のなかの「竪の破法遍」・「従仮入空の破法遍」・「見仮従り空に入る観」について紹介した。「従仮入空」の「仮」には、見仮と思仮の二種があるので、「従仮入空の破法遍」の段は、「見仮従り空に入る観」、「思仮を体して空に入る」、「四門の料簡」の三段に分かれている。
「見仮従り空に入る観」の段は、「見仮を明かす」と「空観を明かす」の二段に分かれており、前回までに、「見仮を明かす」段を説明したので、今回は、「空観を明かす」段以下について紹介する。
④空観(1)
空観は、従仮入空観の省略的表現である。「空観を明かす」段は、「仮を破する観」、「得失を料簡す」、「見を破する位を明かす」の三段に分かれる。
まず、「仮を破する観」では、単の四見(有見・無見・亦有亦無見・非有非無見)、複の四見、具足の四見、無言説(絶言)の四見を破ることが説かれている。『摩訶止観』では、はじめに単の四見のなかの有見を破ることについて詳細に説明している。有見は三仮(因成仮・相続仮・相待仮)を備えており、虛妄で実体がないことを述べたうえで、無明の本(根本)と諸見の末(枝末)がどちらも静寂であり、畢竟清浄であることを「止」といい、無明と法性が相即して虚空のようであると観察して、畢竟清浄であることを「従仮入空観」というと述べている。 続きを読む
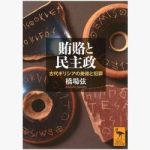
著者・橋場弦氏は古代ギリシア史を専門とする研究者である。本書『賄賂と民主政 古代ギリシアの美徳と犯罪』は歴史学の観点から賄賂の起源と謎を探求した意欲作だ。2008年に山川出版社から刊行されたものを再録したもので、そもそも「賄賂」と「贈りもの」はどこが違うのか、「賄賂」はいつから犯罪と見なされるようになったのか、といった問題を徹底的に掘り下げていく。
本書をひも解きまず驚くのは、古代ギリシアでは「贈りもの」と「賄賂」を表す一般的な言葉が同じ「ドーラ」(dora)であるという点だ。「賄賂」は「贈りもの」の一種として考えられていた。
こうした贈与互酬の慣行のなかに生きていたギリシア人にとって、贈与は単なる財・サービスの移動をもたらすのみならず、それを取り交わす当事者の間に濃厚な人間関係を成立させ、あるいは補強し更新した。贈与は人と人とを結びつける重要な要因であり、逆にそれを拒否することは、人間関係の断絶を意味した。(本書34~35ページ)
贈与互酬というと難しく感じるが、簡単にいえば、相互に贈りものをすることだ。現在の日本でも、お中元やお歳暮、若者の間ではバレンタイン・チョコレートやクリスマスプレゼントの交換が行われている。古代ギリシアではこうした贈りものが盛んに行われていた。
さらに、エリートの間では国内だけでなく国外の要人とも贈りものを交換する伝統があり、その交流は子孫の代にまで及ぶだけでなく、古代東地中海世界では富を循環させる重要な役割をも担っていたという。当時の宗教でも、神々との交流は供儀という贈りものを通じて行われると考えられていた。 続きを読む