



3連休の中日であった2月23日午後7時半から、神戸市内で記者会見がおこなわれた。
こわばった表情で報道陣の前に現れたのは、日本維新の会・岩谷良平幹事長(衆議院議員)、東徹(衆議院議員)、兵庫維新の会・金子道仁代表(参議院議員)の3氏。
冒頭、岩谷幹事長は次のように述べた。
今般、わが党の県会議員にさまざまな報道がなされております。まず増山県議に関しまして、ルールを軽視した極めて不適切な行動があったと認識をしております。そして岸口県議に関しましては、百条委員会副委員長としての自覚に欠けた行動があったというように認識を致しております。
日本維新の会として、これらのことに関しまして、心から深くお詫びを申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。(【動画】「THE PAGE(ザ・ページ)」2月23日)
こう言い終わると、日本維新の会の3氏は深々と頭を下げた。
岩谷幹事長が言及した「わが党の県会議員」とは、いずれも兵庫維新の会に所属する兵庫県議会議員、岸口実、増山誠、白井孝明の3氏のこと。党幹事長が謝罪会見に臨むほどの不祥事。いったい、この3人は何をしでかしたのか。 続きを読む

⑥破法遍(4)
(4)従仮入空の破法遍③
今回は、十乗観法の第四「破法遍」の続きである。破法遍の段落のうち、これまでに「広く破法遍を明かす」のなかの「竪の破法遍」・「従仮入空の破法遍」・「見仮従り空に入る観」について紹介した。「従仮入空」の「仮」には、見仮と思仮の二種があるので、「従仮入空の破法遍」の段は、「見仮従り空に入る観」、「思仮を体して空に入る」、「四門の料簡」の三段に分かれている。
「見仮従り空に入る観」の段は、「見仮を明かす」と「空観を明かす」の二段に分かれており、前回までに、「見仮を明かす」段を説明したので、今回は、「空観を明かす」段以下について紹介する。
④空観(1)
空観は、従仮入空観の省略的表現である。「空観を明かす」段は、「仮を破する観」、「得失を料簡す」、「見を破する位を明かす」の三段に分かれる。
まず、「仮を破する観」では、単の四見(有見・無見・亦有亦無見・非有非無見)、複の四見、具足の四見、無言説(絶言)の四見を破ることが説かれている。『摩訶止観』では、はじめに単の四見のなかの有見を破ることについて詳細に説明している。有見は三仮(因成仮・相続仮・相待仮)を備えており、虛妄で実体がないことを述べたうえで、無明の本(根本)と諸見の末(枝末)がどちらも静寂であり、畢竟清浄であることを「止」といい、無明と法性が相即して虚空のようであると観察して、畢竟清浄であることを「従仮入空観」というと述べている。 続きを読む
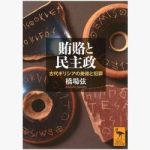
著者・橋場弦氏は古代ギリシア史を専門とする研究者である。本書『賄賂と民主政 古代ギリシアの美徳と犯罪』は歴史学の観点から賄賂の起源と謎を探求した意欲作だ。2008年に山川出版社から刊行されたものを再録したもので、そもそも「賄賂」と「贈りもの」はどこが違うのか、「賄賂」はいつから犯罪と見なされるようになったのか、といった問題を徹底的に掘り下げていく。
本書をひも解きまず驚くのは、古代ギリシアでは「贈りもの」と「賄賂」を表す一般的な言葉が同じ「ドーラ」(dora)であるという点だ。「賄賂」は「贈りもの」の一種として考えられていた。
こうした贈与互酬の慣行のなかに生きていたギリシア人にとって、贈与は単なる財・サービスの移動をもたらすのみならず、それを取り交わす当事者の間に濃厚な人間関係を成立させ、あるいは補強し更新した。贈与は人と人とを結びつける重要な要因であり、逆にそれを拒否することは、人間関係の断絶を意味した。(本書34~35ページ)
贈与互酬というと難しく感じるが、簡単にいえば、相互に贈りものをすることだ。現在の日本でも、お中元やお歳暮、若者の間ではバレンタイン・チョコレートやクリスマスプレゼントの交換が行われている。古代ギリシアではこうした贈りものが盛んに行われていた。
さらに、エリートの間では国内だけでなく国外の要人とも贈りものを交換する伝統があり、その交流は子孫の代にまで及ぶだけでなく、古代東地中海世界では富を循環させる重要な役割をも担っていたという。当時の宗教でも、神々との交流は供儀という贈りものを通じて行われると考えられていた。 続きを読む
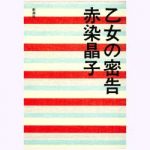
赤染晶子(あかぞめ・あきこ)著/第143回芥川賞受賞作(2010年上半期)
芥川賞選考委員の各選評は毎回、総合月刊誌『文藝春秋』に掲載される。全ての選考委員の選評を読むと、選考会でどのような議論がなされたのか、わずかに垣間見えることもあるのだが、第143回の受賞作、赤染晶子の「乙女の密告」については、例年にないほど白熱した議論が展開されたことが想像された。
選考委員の小川洋子は、
議論の場ではかなり熱い言葉が行き交った。話し合いの中で新たな論点が次々と浮かび上がり、それに一生懸命ついてゆくうち、いつしか作品が受賞に相応しいかどうかの議論であるのを忘れた。賞の問題を超えて、もっと深く小説の世界に入り込み…
と述べている。
『文藝春秋』に掲載される「芥川賞選評」の、選考委員一人あたりの掲載ボリュームは約1ページ弱。そこでそれぞれの候補作について触れることが多いのだが、143回は大変な分量が「乙女の密告」にのみ割かれている。特に、小川洋子と池澤夏樹は2ページにも及ぶ選評をこの作品に割いている。それはまるで文芸評論だ。こんな回は珍しい。
それはなぜか。そこに秘められた才能の大きさに惹きつけられたことはもちろん、もう一つは難解だからだと考えられる。「分からない」などという選評は選考委員には許されないのだろうが、『芥川賞の偏差値』を書いた作家の小谷野敦は(選考委員ではない)、同書で「私にはこの小説が何が言いたいのかさっぱりわからないのである」と告白している。 続きを読む