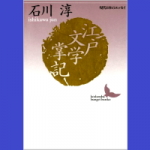あるとき、僕の小説の特徴のひとつは奇想だと批評家にいわれた。それは本人も自覚していたところなので、なぜそうなったのか考え、子供のころ漫画を読み漁ったとおもいあたった。
漫画には奇想があふれている。アイデアが陳腐であれば読者が満足しない。漫画家は懸命にオリジナルなアイデアを求め、それは奇想のおもむきとなる。僕はそういう漫画を日常的に読み、いつか奇想を思いつくようになった。
では、漫画の奇想は、どこからきているのか。そのみなもとは、どこにあるのか。これは論証できない直感なのだが、江戸文学ではないかとおもう。江戸中期以降に発達した、いわゆる戯作である。
戯作は奇想の文学だ。漫画とおなじくアイデアで読ませる。文学史をたどると、江戸におこった戯作は明治に終わる。しかし戯作的想像力は断続することなく、漫画に受け継がれたというのが、僕の見立てだ。
戯作的想像力を相続したのは漫画だけではない。文学でいえば、伝奇小説、そして近年おこったライトノベルもそうだ。いずれも盛大な奇想に満ちた戯作的想像力の産物といえる。
また、ある研究者によれば、戯作は中国文学の影響を受けているという。当時、明が清となり、明代に創作された中国文学が日本へ流入してきた。それを読んだ人々が戯作を書いたというのだ。
すると、日本的な文化であるはずの、漫画、ライトノベルの想像力的な系譜をたどっていけば、広くアジア文明の流れにゆきつく――そんなことを考えていたら、戯作が気になってしかたなく、難渋しながら古い文章を読むようになった。
僕に江戸文学の手引きをしてくれたのは石川淳だ。昭和に活躍した作家で、新戯作派などと呼ばれた。この人の江戸文学の教養は広くて深い。『江戸文学掌記』は、戯作ばかりか、俳諧、狂歌など江戸文学の精華を論じた批評集だ。なかでも、いわば戯作精神を説いた「遊民」の章がいい。
宿屋飯盛という狂歌師がいる。本名は石川雅望(いしかわまさもち)。日本橋で宿屋を営んでいたのだが、ある事件で罪に問われ、江戸を追われた。やがて許されてもどったが、すでに店はたたんでいた。
弟子に岳亭という人物がいて、『狂歌奇人譚』をあらわした。この初編の上下巻は、目録に17人の狂歌師を挙げていて、それぞれの身分を、武家とか商家とか、しるしているのだが、飯盛は遊民となっているのだ。著者は、ここに注目する。
江戸のころには士農工商という身分制があって、誰もがそのなかに分類された。しかし飯盛はどこにも属さない。そこで遊民という身分が発明された。弟子の岳亭は飯盛のことをやたら褒めてもちあげる。それは遊民としるさざるを得ない立場を擁護しているようにみえる。
著者はいう。遊民は、
制度にとっては整理上便利にちがいない。」しかし「このとき岳亭がいかにオマージュの文を書いてとりつくろっても、制度の側から見れば、遊民といふことばのもつ軽侮の意が消えたことにはなりさうもない。この軽侮の意の中には警戒の念もひそむ。遊民、うさんくさいやつ。網をひろげていへば、出自がさむらひだらうと町人だらうと、狂歌師戯作者のともがらは所詮この身分上のワリツケに落ちこんでゆくおもむきである。(ちなみに『狂歌奇人譚』の続篇の目録には、曲亭馬琴も十返舎一九も遊民とある。2人の出自は武家)
だが、遊民だからこそ、できたことがある。それは文学の毒を練ることだ。
この毒は遊民のかたわれと見えるすべての戯作者が肝にしみてうけつぐものである。制度の側からの軽侮こそ、戯作者にとつてはねがつてもない仕事の場にちがひない。地べたに這ひながらも毒を練る。これがわづかに精神の自由といふものか。
「文学の毒」という言い方は、ちょっと時代がかっているし、露悪的な匂いもするけれど、毒は薬にもなる。精神の自由を求めるものは、人を縛ろうとする制度の側からすれば、毒でしかない。しかしそれは人間にとっては、薬である。
遊民は、制度の内に在りながら外に立っている。だから、制度のゆがみ、ほころびがよく見える。それを指摘して、笑い、風刺し、からかう(これが狂歌戯作の役回りのひとつ)。これは、じつに健康で人間的な反応ではないか。
遊民は、明治になって、新たな装いを凝らしてあらわれる。夏目漱石の小説『それから』の主人公・代助は、大学を出ても職に就かずぶらぶらしているので、「高等遊民」といわれる。
彼は父から遊んでいると非難されるが、ものを考える自分は「精神の貴族」だとおもう。ここに江戸から明治へと精神はつながっている。「遊民」論は、こう結ばれる。現在、遊民の末裔はいなくなったが、
江戸このかた遊民の流して来た毒がこれで消えつぱなしになつたと考へるのはおそらく妥当でない。
長篇小説『至福千年』は、まさに遊民の書いた現代の戯作である。
安政5年(1858年)、浅草に仕事場を置く更紗の絵師・更源は、ようやくマリア像の更紗を仕上げた。依頼主に届ける途次、見知らぬ暴漢に襲われ、更紗を奪われそうになるが、弟子の与次郎に助けられた。
与次郎はかすり傷を負い、行きあった遊芸師匠・延登喜から、手当てをしてあげると家に招かれる。そこにいたのは、俳諧師の一字庵・冬峨。旗本くずれの彼は、与次郎の手傷が刃物によるものと見破る――。
物語は、ここから始まる。マリア像の更紗を依頼したのは、「もと稲荷神社の神官で、白狐を使う妖術者の加茂内記」。じつは、内記も更源もともに長崎で学んだ隠れキリシタンだ。
内記には、主宰する秘密結社・千年会によって、地上に「至福千年」の楽土を築くという野望があった。
解説によれば、
至福千年とは、ユダヤ教の黙示文学に描かれた思想であり、最後の審判に先だって、キリストが地上に再臨し、みずから一千年間の地上楽園を実現するだろうという教説
内記は、幕末の混沌とした世情を利用して政府の転覆をねらい、「来たるべき江戸革命の蜂起のために」与次郎を使う。この少年は、向島小梅村の喜六=乞食のかしらと小塚原の遊女の間に生まれた。
内記は、与次郎をキリスト、鳥追いの少女・月光院をマリアの再臨とする思惑。与次郎を教祖にすれば、乞食非人が蜂起にくわわると考えたのだ。江戸の身分制度の外にある彼らこそ、楽土の主体である。
さて、そのくわだてにあらがうのは本所に仕事場を置く松師(植木屋)の松太夫だ。この男も隠れキリシタンでマリア信仰の持ち主なのだが、暴力で世直しをもくろむ内記の思想を異端と見ている。
物語は、内記と松太夫の対立を縦糸に、幕末の歴史(神奈川の開港、安政の大獄、アメリカとの和親条約、桜田門外の変、和宮降家、生麦事件、英艦の鹿児島砲撃など)を横糸に進む。ときとしてフィクションと歴史が交錯し、あやしい閃光が走る。
この仕掛けが、動乱の幕末の世に、ありえたかもしれないもうひとつの現実を浮びあがらせる。制度があらかじめ排除している見えないはずの人々(乞食非人)が、歴史の中心に立つ可能性を想像するのは、極めてスリリングである。
また、内記の弟子で変身術にたけた悪党じゃがたら一角の活躍も見もの。この人物は、後半で重要な役回りを演じる。
さらに、江戸文学の教養を身につけた作者らしく、作中には、適宜に江戸の四季や風物をあしらっていく。
『至福千年』は、文学性が高く、エンターテイメントとしての愉しみもふんだんに盛り込まれている。もちろん、「文学の毒」も。同業の小説家としては嫉妬するばかりである。
お勧めの本:
『江戸文学掌記』(石川淳著/ちくま文庫)
『至福千年』(同/岩波文庫)