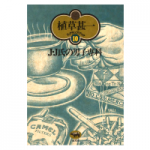大人になりたくなかった。二十歳になるのが憂鬱だった。若いというのは、せつないことでもあるのだ。そういうとき、こんな大人にならなってもいいかな、とおもう人がいた。そのうちの1人が、J・J――植草甚一だった。
J・Jを知ったのは、ちょっと背伸びして買い求めるメンズ・マガジン(エッチなやつじゃありません)だったとおもう。なぜか文章に心を惹かれて、誰が書いたのかを見ると、J・Jの名前があった。そして、いつの頃からか、J・Jの署名のある文章を探すようになった。
僕がぼんやりと憧れたのは、J・Jがすごく生活を愉しんでいることだった。こんな毎日を過ごすことができれば、大人になるのも悪くない、とおもったのだ。
ぼくの家は経堂にあるので、ときどき小田急で新原町田まで散歩に行きたくなる。読みたい本を四十分ばかり電車のなかの空席で読むことができるので仕事の中継ぎ場所としてもいいし、新品カメラを安く売っているディスカウント・ショップがあるので、こないだは六×六の新発売カメラがあるだろうと思って出かけたところ、やっぱりあった。その帰り道にジローのチーズケーキがおいしいので丸のままのを一つ買ってから、なんとなしにデパートふうな店に入って時計のガラスケースをのぞいたところ、ジャガー・ルクルトのホワイトゴールド製小判型懐中時計があって、その濃い紺の盤面がレリーフの細かい装飾になっていたが、それがとても素晴らしい感じなので見とれてしまった。(『J・J氏の男子専科』
)
結局、懐中時計は高いので買わなかったが、代わりにフランスの銀製ボールペンを買ったという。J・Jは散歩が好きなのだが、必ず、何かしら買わないと気がすまない。それで、古本屋巡りをし(おいしいコーヒーを飲ませる喫茶店で古本の味見をし)、ジャズのレコードを漁り、ときには「舶来雑貨」などを買うのだ。
僕はまだ十代のなかばだったが、子供心にも、なんとも羨ましい生活だな、とおもったものだ。
一言でいうなら、J・Jは趣味人である。しかも趣味がいい、と当時の僕は何も知らないのに感じた。少なくとも、J・Jの文章を読むと、そうおもえた。もう一言くわえると、J・Jは、新しい情報や文化のバイヤーであり、趣味のいいセレクトショップである。そこには、人が見とれる品物が並んでいる。J・J自身が、こんな文章を書いている。
パリのアンティークショップ案内を読んでいたら、パリっ子でもよく知らない店を紹介していた。そのうちの一軒が、
とてもシャレてる。子供の肖像が多いが十九世紀の油絵、第一次大戦のとき兵隊が弾薬筒でつくったライター、アール・デコの虫形ペンダント、昔のオモチャや絵本、それからバックルや宝石がたくさん置いてある。
こんな店を出すと楽しいだろうなあ。(同)
いや、実は、J・Jは、こんな店を出していたのである。フロアに並んでいる品物で、おもだったものを紹介してみる。ミステリー小説、映画、モダン・ジャズだ。
『探偵小説のたのしみ』は、ミステリー作家の新人発掘を目的とした文章が収められている。対象になっているのは、欧米の、新しいミステリー小説だ。まだ邦訳されていない良作を30冊探し出したいという。
J・Jは数日に1冊のペースで、ノートをつけ、本に書き込みをしながら読み進めていくのだが、そういう「勉強」がまた、いかにも愉しそうなのだ。評価は☆を20点、★を5点として、☆☆☆☆★を推薦作品とする。
当時まだ新人作家だったジョン・ル・カレの処女作『死者にかかってきた電話』は、作家としての能力は認めながらも、☆☆☆★。ちょっと辛い。ストーリーを紹介しながら、ときおり批評を交えて語っていく。なるほど、ミステリー小説は、こんなふうに読むのかと感心したものだ。
フランスとアメリカの作家のユーモアの感覚を比較し、フランスの作家は、ブールヴァール劇の伝統のおかげで洗練されていると分析するくだりも、ほーっと頷かされる。
また、注目している新人が作家として成長し、作品が良くなっているのを知ると、無条件にうれしくなって☆☆☆☆★★★をつける。この文章を連載していた雑誌が休刊になったせいで、新人発掘の作業は途中で終わったが、本書にはJ・Jのミステリー小説への深い愛情が感じられる。1960年代の、欧米のミステリー小説の熱気が窺える。
『クライム・クラブへようこそ』は、「勉強」の成果といえるだろうか。これはミステリー小説の老舗・創元社から刊行されたミステリー叢書『クライム・クラブ』と『現代推理小説全集』に付されたJ・Jの解説を収めている。両方とも作品を選んだのはJ・Jだ。
フランス、アメリカ、イギリスの、当時としては新しい作家の作品が並ぶ。発表されてから半世紀を過ぎた現在では、ミステリー小説の古典といえるものもあって、『探偵小説のたのしみ』と『クライム・クラブへようこそ』を読むだけでも、大いに「勉強」になる。
『サスペンス映画の研究』では、ミステリー小説の読者が増えてきたが、この中には映画ファンが実に多い、それは「サスペンスの魅力」という共通点があるからだという。ミステリー小説好きのJ・Jも映画ファンだ。書名に「研究」とあるが、抽象的な論ではない。具体的な作品に即したエッセーなので、やはり、おもしろい。
サスペンスとは何か? シャーロック・ホームズの映画の一場面などを引用して、「なにかが起こるだろうという期待」「映画をみているときに観客につたわってくる不安感」と述べる。うーん、分かりやすい。
サスペンス映画の巨匠といえばアルフレッド・ヒッチコックだ。J・Jによれば、彼が最初に撮ったサスペンス映画は『下宿人』(1926)で、この作品からほぼ10年後の『三十九夜』までのあいだに、この監督の手でサスペンス映画の文法がつくられた。
ただ、その前史はあって、サイレント映画末期のドイツ映画で、日本では「怪奇映画」と呼ばれていたものが挙げられる。これらの映画には、サスペンス映画のような、「不安と緊張をあたえる場面に、しばしば出くわした」という。なるほど、と納得させられる。
さらに、ミステリー小説とサスペンス映画の結びつきを考え、フィルム・ノワールの世界を探訪し、J・Jの「研究」は興味が尽きない。
街の中を歩きながら、ああ、きょうは古本をだいぶ買ったなと思うと、うちへ帰るまえにコーヒーが飲みたくなるものだ。歩きすぎて、すこし疲れているし、おいしいコーヒーをだす喫茶店にはいって、買った本をパラパラとめくるのが、もう長いあいだ、ぼくの癖になってしまった。
モダン・ジャズがすきな人は、見わたしたところ、本がすきな若い人たちが多いようだ。
『コーヒー一杯のジャズ』は、こんなJ・J調の書き出しで始まる。J・Jのセレクトショップに並ぶジャズ・ミュージシャンは、セロニアス・モンク、チャーリー・ミンガス、オーネット・コールマン、ジョン・コルトレーンなどだ。
モダン・ジャズというものは、なにかひとつうなってしまうような演奏にぶつかれば、それがきみたちをとりこにしてしまい、もっとすごいのはないかと聞きあさるようになっていくものだ。
このモダン・ジャズについての文章も、「平凡な思い出」に過ぎない。ともかくレコードを聴いておくれ。
自分の趣味を押しつけない。ミステリー小説にしても、サスペンス映画にしても、モダン・ジャズにしても、これは、おいしい、とおもったものを、単純に、おいしい、というだけだ。通人が素人に教えを垂れるような権威的なところがない。だから、読んでいて爽やかなのだろう。
J・Jはモダン・ジャズも、新人のレコードをできるだけたくさん聴いて、「勉強」しようと書いている。いうまでもなく、この「勉強」も、実に愉しそうだ。
モダン・ジャズと映画について論じたエッセーがおもしろい。『クライム・クラブへようこそ』で取り上げられた『死刑台のエレベーター』というミステリー小説が、1958年に映画化された。この映画がジャズファンのあいだで、大きな話題になった。マイルス・デイビスが音楽をつけたのだ。
監督のルイ・マルは、撮影が進行しているあいだ、ずっとマイルスのレコードを聴いていて、彼が音楽をつけてくれたら、と夢想していた。すると、本人が突然パリにやって来たので、空港でつかまえて依頼し、夜の9時から朝の5時にかけて即興演奏を録音したという。
J・Jはマイルスのトランペットを、
頭がしびれるような印象をあたえる。
と激賞している。おいしい、といっているのだ。
ミステリー小説がサスペンス映画になり、その映画にモダン・ジャズの音楽がつけられる。J・Jの著作を読んでいると、はからずもその過程を追って、文学と映画と音楽の関係を考えさせられる。これは関心の幅の広いJ・Jならではないだろうか。
ともかくJ・Jは、海の向こうの、おいしいもの、おもしろいことを、どっさり知っていた。そして、さり気なく、これ、どうだい? と差し出してくれた。ネットで世界の情報や文化が瞬時に手に入る現在とは違って、こういう存在は貴重だった。
さて、J・J――植草甚一は、こんな大人にならなってもいいかな、とおもわせてくれた人物だった。だんだん当時の彼に年齢が近づいてきて、自分は若い人にどう映っているだろうかと考えてみると、なんとも心許ない。
お勧めの本:
『J・J氏の男子専科 植草甚一スクラップブック10』(植草甚一/晶文社)
『探偵小説のたのしみ 植草甚一スクラップブック31』(植草甚一/晶文社)
『クライム・クラブへようこそ 植草甚一スクラップブック18』(植草甚一/晶文社)
『サスペンス映画の研究 植草甚一スクラップブック5』(植草甚一/晶文社)
『コーヒー一杯のジャズ 植草甚一スクラップブック23』(植草甚一/晶文社)