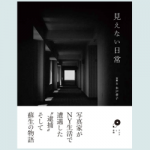封印していた国外への旅
木戸孝子は、近年、欧米の写真展で評価が高まっている写真家の1人である。
特に注目されているのは、2022年から発表しているシリーズ〈Skinship〉で、自身の出産と子育ての経過、家族の親密さをセルフポートレートの手法で撮ったもの。
2024年6月、高知県四万十市に暮らす木戸のもとに、ベルギーの有名ギャラリー「IBASHO」のディレクターから連絡があった。「IBASHO」は木村伊兵衛、土門拳、石元泰博、細江英公、森山大道といった日本の優れた写真家をヨーロッパに紹介してきたギャラリーだ。
ディレクターのアンマリーは、前年の「KYOTOGRAPHIE」のポートフォリオ・レビューで木戸の作品を見ていた。
アンマリーからの連絡は、2024年11月に開催されるヨーロッパ最大のアート写真フェアである「パリ・フォト」に、木戸の作品を展示したいというものだった。
今回の「パリ・フォト」の会場は巨大なガラス天井が印象的なグラン・パレ。1900年のパリ万博のために建設された施設で、2024年パリ五輪ではフェンシングなどの試合会場にも使用された。
34カ国の240ギャラリー・出版社のブースが並び、お抱えアーティストの作品が展示されている。「IBASHO」のブースに並んだのは、木戸の作品シリーズ〈Skinship〉だった。
この「パリ・フォト」に出品するためには、写真界の大御所たちで構成される選考委員会に企画書を提出し、そこで選ばれなければならない。写真家としての大きな晴れ舞台。11月、木戸は家族とともにパリに赴いた。
じつは、木戸は2008年にニューヨークから日本に戻ったあと、国外に出ることをずっと封印していた。帰国後に子どもが生まれたということも大きかったが、それ以上にニューヨークでの〝出来事〟がトラウマとなり、怖くて出られなかったのだという。
ニューヨークでの「3人暮らし」
木戸孝子は1970年、高知県生まれ。創価大学を卒業したあと都内のプロラボ勤務を経て写真家となる。2002年に渡米し、ニューヨークのICP(International Center Photography)を卒業。そのままニューヨークのスタジオに勤務する傍ら自身の作品も撮り、『高知新聞』に連載を持つなどしていた。
木戸孝子の初のエッセー集となる本書は、彼女がニューヨークで体験した思いもかけない〝出来事〟の一部始終を綴ったものだ。同時にこの〝出来事〟こそが、今日の彼女が国際的に高い評価を得ている〈Skinship〉シリーズを生み出すきっかけとなった。
ICPを卒業したあと、木戸が労働ビザを得て働いていたのは、ニューヨークでも一流の白黒銀塩写真の現像所だった。クライアントは国際的な写真家たち。扱うのは数十万円から数百万円の作品ばかり。
日本人のボーイフレンドもできて、まもなく一緒にアパートで暮らすようになった。米国の大学を卒業し、彼女よりずっと前からこの国で暮らしていた男性だった。
ボーイフレンドには、前妻とのあいだに日本に暮らす幼い息子がいた。2007年の夏休みに、10歳になるその息子がニューヨークに遊びに来た。彼はよほど居心地がよかったのだろう。パパとその彼女と一緒にニューヨークでの生活を続けたいと願った。
母親であるボーイフレンドの前妻も了承し、3人での暮らしが始まる。
エネルギーを持て余した子どもとの新しい生活は、新鮮な一方で疲れることも多かった。カメラに興味を示したので、木戸はコンパクトカメラを貸してあげた。
好奇心いっぱいの10歳は、さっそくカメラを三脚に立ててセルフタイマーを使うことまで覚え、いろんなものを撮っていた。木戸にとっては生活のなかにカメラがあることは自然なことだったので、子どもが何を撮っているのかにもいちいち気にとめていなかった。
3歳からパパと離れて暮らしていた男の子にとって、パパとその彼女との生活は、楽しいだけでなく、きっと欠けていた何かを埋め戻す時間でもあったに違いない。
一緒にお風呂に入ったあとは、裸のまま走り回る子どもを追いかけて髪を拭いてやった。
ちょうど日本では「クレヨンしんちゃん」が人気だったし、あるいは「おしりかじり虫」という歌も流行っていた。10歳の男子はその歌を歌いながら、おどけてお尻にかじりつくしぐさをし、クレヨンしんちゃんのギャグを真似て木戸の尻に〝カンチョー〟をする。さらに子どもは、そんな自分のやんちゃの一部始終をセルフタイマーで撮ったりもしていた。
当時の木戸は二眼レフのローライフレックスを使って白黒フィルムで作品を撮っていた。白黒は自分で現像する。ただ、カラーフィルムを現像する設備は整えていなかったので、そちらはプロラボに出していた。
子どもに貸し与えていたコンパクトカメラにはカラーフィルムが入っている。そのうち、現像に出していないままのフィルムがいくつか溜まっていたが、もちろんいつ何を撮ったものかも判然としない。
子どもの遊びで撮らせたものだからと、木戸は深く考えずに近所のドラッグストアに現像に出した。これが運命の分かれ道になった。
「何をしたか話さないほうがいい」
2007年10月1日。ドラッグストアから現像が仕上がったという電話があったので、木戸は店に出向いた。なぜか、そこには警官がいて、木戸はその場で「逮捕」され、そのまま拘置所に収容された。
木戸はそれを「日常からの死」「臨死体験に近い」と記している。
日常は突然断ち切られた。家族にも友だちにも会えないし、話もできない。仕事を休むための電話もできなかった。自分の服もお金もない。時計がなくて、時間もわからない。パーマの予約もしていたのに。クレジットカードの支払いは? 連続していた日々が、ブツッと途切れたような感覚。
お金も、肩書きも、職業も、社会的地位も、化粧も、家族も、すべて剝ぎ取られる。死ぬ時には持っていけないものリストのようだ。名札には、宗教だけが記されていた。(本書)
何が起きたのか――。警察に通報したのはドラッグストアだった。なぜなら、現像されたフィルムには、風呂上がりの裸の子どもが写っていたからだ。木戸を引き取りに警察に出向いたボーイフレンドも、その場で逮捕された。
昭和の日本で育った木戸やボーイフレンドからすれば、親が幼い子どもと一緒に風呂に入ることはあたりまえのことだった。
フィルムに収まっていたのは、プライベートな空間のなかでの〝親子〟の微笑ましい時間のはずだった。ところが、ドラッグストアと警察は、木戸たちが児童への性的虐待をおこなっていると見做したのだ。
宗教的なバックグラウンドの違いから、米国では子どもが3歳くらいになると、親は子の前で裸を見せない。むろん、一緒に裸で風呂に入ることもない。
当局がもっとも問題視したのは、風呂上がりの木戸と少年がベッドサイドに並んで座っている1枚だった。夜の室内で子どもがセルフタイマーで撮ったものだったが、シャッタースピードが遅く、ブレていて、現像の具合で赤色の強い怪しい光に包まれていた。
日米の文化・風習の違いといえば、単にそれだけの話だった。しかし、米国の警察官がこの写真を見れば、それはこれからおぞましいことが起きる光景を想起させるものでしかなかったらしい。
クレヨンしんちゃんの「カンチョー」写真も、罪状一覧には「子どもがTakakoのお尻の穴に指を突っ込んだ」と記載されていた。
当局にクレヨンしんちゃんの「チンコプター」を説明するため、日本から「クレヨンしんちゃん」のDVDを取り寄せる必要があったが、いざ手配をしようとして米国では「クレヨンしんちゃん」が児童ポルノに分類されていることを知った。
なにもかもが、まるで笑い話のような〝誤解〟に基づくものだったが、刑務所で親しくなった囚人仲間からは、自分の罪状について刑務所では「話さないほうがいい」と念押しされた。小児性犯罪者と見做されれば、囚人からリンチを受けるというのだ。
木戸とボーイフレンドが収容されたのは、マンハッタンのすぐそばにあるランカーズアイランドの拘置所。世界でも最大規模の拘置所の1つで、衛生状態などの悪さでは全米でもワースト10入りしていた。
ちなみに、木戸とボーイフレンドはランカーズアイランドのすぐ近くに住んでいたのだが、そこに巨大な拘置所があることなど露も知らなかった。
書名に込められた2つのメッセージ
本書の大部分は、この世間から隔絶された拘置所や、その後に再び収容されたハドソン郡刑務所内での出来事であり、無実を訴える木戸と、まったく耳を貸さない当局との息詰まる攻防である。
『見えない日常』には、木戸自身の生活のすぐそばに存在しながら見えなかった、ランカーズアイランド拘置所内部の日々という含意がある。
身に覚えのない罪状で収容されている者たちの存在や、当局の杜撰な対応など、塀の内側を体験した人間にしか書けない内容が続く。
エッセーではあるものの緊張感のある筆致で、ほとんどノンフィクションを読んでいるような感覚の展開に引き込まれる。
自分の無実を説明するために、あらためて日米の文化の違いを当局に語りながら、やがて木戸は自分が話そうとしていることは「スキンシップ」についてではないかと気づき始める。
危険な刑務所での長期収監を免れる唯一の方法は、司法取引に応じて〝有罪〟を認め、国外退去処分を受け入れることだった。
『見えない日常』という書名のもう1つの含意は、日米の文化の違い。すなわち、日本では幼い子どもと親や祖父母が一緒に風呂に入ったり、暑い時期に半裸で過ごすことが長いあいだの風習だったが、米国ではそれは犯罪行為と見なされる。
日本人と米国人は互いをよく知っていたつもりでいたはずなのに、そこには両者の〝見えない日常〟が横たわっていた。
2008年4月、木戸とボーイフレンドは成田空港に着く。その後、結婚生活を始めた仙台の地で、今度は東日本大震災を経験。各国から来た報道関係者のなかには、ICP時代の仲間もいた。
木戸は被災者でありながら、写真家として被災地を撮影して歩いた。
撮影を続けるうちに、私は被災地で、何ものにも壊せない美しさを見た。亡くなった人々の命の美しさを見たのだと思った。(本書)
のちに、そのなかの1枚は、芥川賞を受賞した佐藤厚志『荒地の家族』の表紙とカバーに使われることとなる。
一見、あまりにも不運で理不尽な災厄に見舞われたかに見える木戸のニューヨークでの最後の1年。写真家としてのニューヨークでのキャリアを断ち切ったのは、皮肉なことに「写真」だった。
自身に降りかかった忌まわしい出来事の意味を考え続けていた木戸は、日米の〝見えない日常〟に気づき、しかしそれが日本人として、女性として、母親としての自分のアイデンティティに深く根差すものであることを見出していく。
そこから生まれた作品シリーズ〈Skinship〉は、今や米国を含む西洋社会で注目を集めているのである。
そして、時を経て1冊の書籍として振り返ると、その場その場で起きていた出来事のすべてが、彼女を写真家として国際的な舞台へ飛翔させるための天の配剤であったことに気づかされる。
あるいは、本当に豊かで強い人間とは、いかなる災厄をも財産に変えることのできる人をいうのかもしれない。
本書は鳳書院のウェブメディア「アジアと芸術digital」に、2023年8月から1年余り連載されたもの。展覧会ポスターや美術系書籍を多く手がけてきたSTORKがブックデザインと装丁を手がけ、スタイリッシュな仕上がりとなっている。
木戸孝子サイト Takako Kido Photography
「本房 歩」関連記事①:
書評『歌集 ゆふすげ』――美智子さま未発表の466首
書評『法華経の風景』――未来へ向けて法華経が持つ可能性
書評『傅益瑶作品集 一茶と芭蕉』――水墨画で描く一茶と芭蕉の世界
書評『もし君が君を信じられなくなっても』――不登校生徒が集まる音楽学校
書評『LGBTのコモン・センス』――私たちの性に関する常識を編み直す
書評『現代台湾クロニクル2014-2023』――台湾の現在地を知れる一書
書評『SDGsな仕事』――「THE INOUE BROTHERS…の軌跡」
書評『盧溝橋事件から日中戦争へ』――日中全面戦争までの歩み
書評『北京の歴史』――「中華世界」に選ばれた都城の歩み
書評『訂正可能性の哲学』――硬直化した思考をほぐす眼差し
書評『戦後日中関係と廖承志』――中国の知日派と対日政策
書評『シュリーマンと八王子』――トロイア遺跡発見者が世界に伝えた八王子
書評『科学と宗教の未来』――科学と宗教は「平和と幸福」にどう寄与し得るか
書評『日本共産党の100年』――「なにより、いのち。」の裏側
書評『差別は思いやりでは解決しない』――ジェンダーやLGBTQから考える
「本房 歩」関連記事②:
書評『ヒロシマへの旅』――核兵器と中学生の命をめぐる物語
書評『アレクサンドロスの決断』、『革命の若き空』(同時収録)
書評『新装改訂版 随筆 正義の道』――池田門下の〝本当の出発〟のとき
書評『希望の源泉 池田思想⑦』――「政教分離」への誤解を正す好著
書評『ブラボーわが人生4』――心のなかに師匠を抱いて
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(上) まずは会長自身の著作から
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(下) 対談集・評伝・そのほか
書評『希望の源泉・池田思想⑥』――創価学会の支援活動を考える
書評『創学研究Ⅱ――日蓮大聖人論』――創価学会の日蓮本仏論を考える
書評『公明党はおもしろい』――水谷修が公明党を応援する理由
書評『ハピネス 幸せこそ、あなたらしい』――ティナ・ターナー最後の著作
書評『なぎさだより』――アタシは「負けじ組」の組員だよ
書評『完本 若き日の読書』――書を読め、書に読まれるな!
書評『ブラボーわが人生 3』――「老い」を笑い飛ばす人生の達人たち
書評『日蓮の心』――その人間的魅力に迫る
書評『新版 宗教はだれのものか』――「人間のための宗教」の百年史
書評『もうすぐ死に逝く私から いまを生きる君たちへ』――夜回り先生 いのちの講演
書評『今こそ問う公明党の覚悟』――日本政治の安定こそ至上命題
書評『「価値創造」の道』――中国に広がる「池田思想」研究
書評『創学研究Ⅰ』――師の実践を継承しようとする挑戦
書評『法華衆の芸術』――新しい視点で読み解く日本美術
書評『池田大作研究』――世界宗教への道を追う