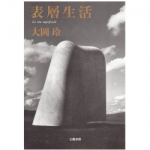人間とコンピュータの関係。その危うさに切り込んだ挑戦的作品
大岡玲(あきら)著/第102回芥川賞受賞作(1989年下半期)
傍観者が語る異常さ
第102回の芥川賞は、W受賞となった。前回取り上げた『ネコババのいる町で』と共に、大岡玲の『表層生活』が受賞。枚数は171枚。東京外大在籍当時から小説を書き始め、2作目の『黄昏のストーム・シーディング』が三島由紀夫賞を獲り、その翌年に芥川賞を受賞。31歳の時だった。
テーマは、コンピュータを筆頭とするテクノロジーが、人間の思考や価値観にどのような影響を与え変容するか、ということだ。当時は、まさにコンピュータが私たち一般人の生活の中にも深く入り込みつつあった時代だったので、こうしたテーマはあらゆる場面で話題になることが多かったはずだ。そういう意味では、時代を切り取る文学作品としては実にタイムリーだったに違いない。
今は、私たちもコンピュータのある生活をすっかり受容しているので、それに対する不安というものは忘れ去られているかのような状態だ。だからこそ、『表層生活』のなかに描かれている不安や恐れは、今さらながらに新しく感じる部分がある。
――優秀な頭脳を持つ〝計算機〟と、その同級生だった平凡な「ぼく」。二人は、社会人になってから久しぶりに出会う。「ぼく」は、〝計算機〟の変容に薄々気づきながらも、コンピュータのシミュレーションやサブリミナルビデオを用いて人を支配しコントロールしようとする〝計算機〟の試みにつき合わされることになった。「ぼく」は次第に、その恐ろしさに気づき距離を置こうとし始めたのだが、すでに後戻りできないところまで進んでいた〝計算機〟の異常性は、最後に悲しい結末を迎える――。
主人公を〝計算機〟にするのではなく、「ぼく」に傍観者として語らせることで、〝計算機〟の異常さを客観的に語っていくことに成功した。
けれども、設定に無理を感じてしまう部分が気になった。たとえば、「弱き者を差別し、強き者を選び取るため」という目的を〝計算機〟が持つに至った経緯が不明瞭なので、唐突感がありすぎて、それが物語への入り込み方を阻害してしまっている。この点について、選考委員の古井由吉は、
仕掛けが楽観的にすぎないか。シミュレーションによりかくも単刀に現実突入を図る『専門家』というのは、人物の設定としてそもそも無理なのではないか
と指摘している。非日常的な物語の難しさだろう。
それでも、その執念にも似た粘りの筆で書き進んでいくことで、作者が描こうとしているものの世界に引き込まれていき、最後は私も、「ぼく」が感じた哀しみを幾分か共有することができたのだ。
新しさへの挑戦
「芥川賞作品はおもしろくない」という人がいる。私も少なからずそう思う場合がある。おそらくそれは、芥川賞が感動やおもしろさよりも、文学としての〝新しさ〟を求めているからだろう。文学に限らず芸術作品は既視感のあるものを喜ばない。今まで見たことのないものを見たいと思う。新進気鋭の作家を求める芥川賞ではなおさらだ。
新しいものを新しい手法で描こうとすると、どうしても扱うものが枝葉末節なものになりがちなのではないか。そうすると、永遠不変の骨太な、腹に響くような深い感動をもたらすものになりにくい。
『表層生活』についても、一般読者の評価は分かれている。ネットでは「分かりづらい」という感想が多い。作家の小谷野敦などは、その著書『芥川賞の偏差値』のなかで、
何か退屈な小説を読みたいという人がいたらお勧めしたいくらいで、これで前衛的なつもりなのか
と酷評している。
だがしかし、それでも芥川賞として選考委員がこの作品を掬いあげたのは、「挑戦的」だったからだろう。
選考委員の河野多惠子は、
作者が前人未到の分野に挑んでいることは確かである
と述べ、黒井千次は
作者が一貫して現代そのものに取り組もうとする姿勢を支持したい
と述べ、田久保英夫は
これは現代生活に潜む切実な主題でもあって、それに執拗にとりくむ力業に、私は注目した。大岡氏の才能は、ねばりづよい思念的な追求と、新鮮な描写力だ
と述べている。
私がラストシーンで心を動かされた〝計算機〟と「ぼく」の哀しみは、つまり、数理の先に秩序をつかめると信じた〝計算機〟が秩序をつかむどころか、周囲のあらゆる事象から冷酷に拒絶された事実にあった。理系能力が皆無の私にも何かしらを感じることのできた『表層生活』も結局は、人間という古典的なものを扱っているものなのだ。
芥川賞を読む:
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』